要保護児童対策地域協議会(要対協)をわかりやすく解説!目的や対象者、自治体の取り組み例は?
要保護児童対策地域協議会をご存じでしょうか?
一般にはあまり聞き慣れない協議会かもしれませんが、じつは私たちの生活、とりわけ子どもたちの安心・安全な生活を守る上で重要な役割を担っている組織です。
また、日本国内のほぼすべての自治体に設置されており、多くの専門家や組織が関係する協議会でもあります。
そこで今回は、要保護児童対策医地域協議会の目的や役割、対象者についてわかりやすく紹介します。
これまでご存じなかった方も、この記事を参考にして「地域の取り組み」に少しでも関心を持っていただければ幸いです。
要保護児童対策地域協議会とは?子どもを守る地域の絆

要保護児童対策地域協議会(要対協)は、2004年(平成16年)の児童福祉法改正によって法定化された、
子どもたちを守るための地域ネットワークです。
2007年(平成19年)の法改正では、市町村等での設置が努力義務化されました。
協議会の主な目的は、虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童等の早期発見と適切な保護を図ることとし、児童福祉法第25条※の2に位置付けられています。
児童相談所、学校、教育委員会、警察など、様々な関係機関が連携して子どもたちを支援します。
2013年(平成25年)4月1日時点で、実に98.9%の市町村で設置されており、現在も、多くの地域で子どもたちを守る取り組みが進められている重要な協議会です。
※e-Gov法令検索|児童福祉法
参照|厚生労働省|第1章 要保護児童対策地域協議会とは
参照|こども家庭庁|要保護児童対策地域協議会のあり方に関する調査研究報告書(令和5年3月)
要保護児童対策地域協議会は誰のため?
支援の対象となる子どもたち
要対協が支援の対象とする子どもたちは、主に以下の3つのカテゴリーに分類されます。
- 要保護児童
- 要支援児童
- 特定妊婦
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
要保護児童:緊急の支援が必要な子どもたち
要保護児童とは、18歳未満の子どもで、保護者がいない、または保護者に監督・保護させておくことが不適当だと認められる子どもたちを指します。
具体的には:
- 家出や死亡、離婚、入院、服役などによって保護者が不在の子ども
- 虐待を受けている子ども
- 非行や情緒障害がある子ども
など。
これらの子どもたちは、緊急性が高い場合、児童相談所などでの一時保護が行われることもあります。
要支援児童:見えにくい支援が必要な子どもたち
要支援児童は、すぐに保護する必要はないものの、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子どものことです。
例えば:
- 育児不安(育児に関する自信のなさ、過度な負担感等)を抱える親のもとで育つ子ども
- 養育に関する知識が不十分な親のもとで、不適切な養育環境に置かれている子ども
など。
表面上は問題がないように見えても、
実は支援を必要としているケースが多いため、十分な配慮が必要です。
特定妊婦:生まれる前から支援が必要な赤ちゃん
特定妊婦とは、出産後の養育について、出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のことです。
例えば:
- 収入基盤が安定せず、貧困状態にある妊婦
- 知的・精神的障害などで育児困難が予測される妊婦
- DVや若年妊娠など、様々な複合した問題を抱えている妊婦
など。
全国に約8,000人いるといわれ※、その数は年々増加傾向にあります。
※恩賜財団済生会|ソーシャルインクルージョンを考えるWebメディア|特定妊婦
要保護児童対策地域協議会(要対協)の構成員:子どもを守る多様な専門家たち

要対協は、子どもに関わる様々な分野の専門家で構成されています。
主な構成員には以下のような方がいます。
それぞれの分野ごとの主な職種を見てみましょう。
児童福祉関係
- 市町村の児童福祉主管課
- 児童相談所
- 福祉事務所(家庭児童相談室)
- 保育所(地域子育て支援センター)
- 児童養護施設等の児童福祉施設
- 主任児童委員、民生・児童委員
教育関係
- 教育委員会
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
保健医療関係
- 市町村の母子保健主管課、保健センター
- 保健所
- 医師会、歯科医師会、助産師会、看護協会
- 医療機関(クリニック、中核医療機関)
警察・司法関係
- 警察署
- 弁護士会、弁護士
- 法務局
- 人権擁護委員会
その他
- NPO、ボランティア、民間団体
これらの専門家が連携することで、子どもたちをより多角的に支援することが可能になります。
参照|こども家庭庁|要保護児童対策医地域協議会の概要
要保護児童対策地域協議会(要対協)の目的:子どもを守る7つの力
要対協には、以下の7つの重要な目的があります※。
- 要保護児童等を早期に発見すること
- 要保護児童等に対し、迅速に支援を開始すること
- 各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化を図ること
- 情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、役割分担について共通の理解を得ること
- 関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わることのできる体制づくりをすること
- 情報の共有化を通じて、関係機関等が同一の認識の下に、役割分担しながら支援を行うため、支援を受ける家庭にとってより良い支援が受けられやすくなること
- 関係機関等が分担をしあって個別のケースに関わることで、それぞれの機関の限界や大変さを分かち合うことができること
これらの目的を達成することで、子どもたちを効果的に支援し、安全・安心の確保に取り組みます。
※厚生労働省|市町村児童家庭相談援助指針について:第4章 要保護児童対策地域協議会|「要保護児童対策地域協議会の意義」を参照
参照|こども家庭庁|「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)」の実践事例集
支援の流れ:子どもを守る6つのステップ
要対協における支援の流れは、主に以下の6つのステップで進められます。
1、相談・通報受理
- 関係機関等や地域住民からの要保護児童の相談、通報を事務局が集約。
2、緊急度判定会議(緊急受理会議)の開催
- 相談・通報受付票をもとに、事態の危険度や緊急度の判断を行う。
3、調査
- 具体的な援助方針等を決定するために必要な情報を把握するため、調査の実施。
4、個別ケース検討会議の開催
- 支援に当たっての援助方針、具体的な方法及び時期、各機関の役割分担、連携方法、当該事例に係るまとめ役、次回会議の開催時期などを決定。
5、関係機関等による支援
- 決定された援助方針等に基づき、関係機関等による支援を行う。
6、定期的な個別ケース検討会議の開催
- 適時適切に相談援助活動に対する評価を実施し、
それに基づき、援助方針等の見直しを行います。
また、相談援助活動の終結についてもその適否を判断。
自治体により異なるものの、概ね上記の手順で実施されるのが一般的なようです。
参照|こども家庭庁|要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワークスタートアップマニュアル)
子どもの居場所:貧困や虐待から子どもを守る安全な場所
要対協の活動と関連して、近年注目されているのが「子どもの居場所」です※。
これは、貧困や虐待などの厳しい家庭環境で生活する子どもたちに、主に食事、入浴、学習などの支援を行う場所のことです。
そのため、子どもの居場所は、子どもたちの人権を守り、健全な育ちと社会的自立につなげるための重要な役割を果たしています。地域の大人たちが協力して運営することで、子どもたちに安全で温かい環境を提供しているわけですね。
※こども家庭庁|こどもの居場所づくり
要保護児童対策地域協議会の事例
冒頭でもお話ししたように、要保護児童対策医地域協議会は全国の自治体で実施されています。
しかし、実際にどのような方針で行われているのかについて、見たことがない方も多いのではないでしょうか。
そこで以下では、自治体における要保護児童対策医地域協議会の事例を紹介します。
東京都における要保護児童対策地域協議会
東京都では、児童虐待対策事業の一環として、要保護児童対策医地域協議会が設置されています※。市区町村の子供家庭支援センターが調整機関となり、民間団体を含むさまざまな関係機関と連携して対策を行なっています。
※東京都|児童虐待対策事業
横浜市おける要保護児童対策地域協議会
横浜市でも、児童虐待対策事業の推進及び全市の総合調整を目的として、平成8年6月に設置されました。
その特徴は、
・市民局
・教育委員会事務局
・こども青少年局等
の3層構造で構成されている点にあります。
また、さまざまな専門家が連携することにより、質の高い、多角的な支援が実施される点も特徴です。
横浜市|要保護児童対策地域協議会とは
要保護児童対策地域協議会まとめ:地域で子どもを守る、私たちにできること
要保護児童対策地域協議会は、子どもたちを守るための重要な仕組みです。
しかし、この仕組みが効果的に機能するためには、私たち大人一人ひとりの協力が欠かせません。
子どもたちの様子に気を配り、何か気になることがあれば躊躇せずに相談する。
それが、子どもたちを守る第一歩となるはずです。
そのために、地域全体で子どもたちを見守り、支えていく。
そんな社会を作っていくためにも、この記事が「一人ひとり何ができるか」を考えるきっかけになれば幸いです。
要保護児童対策地域協議会をもっと詳しく知りたい方に
この記事はさまざまな情報を元に作成しています。
そのため、「要保護児童対策医地域協議会についてもっと知りたい!」という方、あるいは「自分にも何かできるかもしれない」と思われた方は、それぞれのリンク先を参照ください。



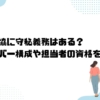


最近のコメント