スマホ依存は危険!その影響や症状、解決のコツやチェックリストを簡単に解説します
インターネットや端末の発展と共に、スマホ依存が社会問題となっています。
スマートフォン1つあれば、SNSで膨大な情報を収集できたり、ゲームが楽しめる反面、使用頻度や使い方によっては利用者にデメリットが生ずることも少なくありません。
「自分は大丈夫!」なんて思っていても、
・「スマホが近くにないと不安」
・「理由もないのについチェックしてしまう」
・「なんとなく身体の調子が悪い」
と感じている人は、もしかしたら依存傾向にあるかもしれません。
そこでこの記事では、スマホ依存がもたらす影響や症状、解決のコツについて簡単に解説します。
スマホ依存は危険!

まずは「スマホ依存とは何か?」についてみてましょう。
現在のところは病気とみなされていませんが、使いすぎた場合には、身体面や精神面において重大なデメリットがあるので、節度や基準を設けて使用することが重要です。
そもそも依存症とは?
依存症とは「特定の何かに心を奪われ、『やめたくても、やめられない』状態になること」です※。
その対処は多岐に渡りますが、代表的なものとして、
・アルコール
・タバコ
・ギャンブル
などは皆さんも聴いたことがあるのではないでしょうか。
さらに依存症には大きく分けて、
1、物質への依存
2、プロセスへの依存
の2種類があり、いずれも本人や周囲の人に悪影響が出ることが特徴です。
現在のところ「スマホ依存」は具体的な病気として認めていないものの、「依存傾向にある」として医療機関を受診する人も増えてきています。
またMMD研究所が2022年に行った調査※によると、スマホを利用する人の20.9%が「かなり依存している」と回答し、49.0%が「やや依存している」という結果となりました。
そのため、身体的・精神的なリスクを避けるためにも、スマホの使用には一定のルールを設ける必要があるかもしれません。
※MMD研究所|2022年スマホ依存と歩きスマホに関する定点調査
依存症は医療機関での治療が不可欠
依存症の恐ろしい点は、一度陥ると本人によるコントロールが困難になることにあります。
周囲の人々からやめるように促された際に「抵抗感がある」あるいは、「それがないことに不安を覚える」場合は、依存症の傾向が出ているかもしれません。
依存症は自分の意思ではコントロースしにくいものです。
そのため、周囲の理解や適切な対応、そして医療機関での治療が不可欠となります。
こんな症状があればスマホ依存の疑いあり
1台で何役もこなせるスマートフォン。
SNSでの利用や動画視聴、あるいはオンラインゲームに没頭する人も多いのではないでしょうか。
たしかにSNS上でのコミュニケーションは有意義ではありますが、あまりにも使用頻度が多い場合や、手元にないと不安で仕方がないと感じる方は、スマホの使用方法を考え直す必要があるかもしれません。
そこで以下のような症状が当てはまる場合は、もしかしたら依存傾向にある可能性がるので、チェックしてみてください。
・お風呂やトイレにも持ち込んでしまう
・食事に集中せず、スマホを見ながら食べてしまう
・通知がないのに通知が来たように感じる
・歩きスマホをしてしまう
・寝る直前、起床後にスマホを見る
・充電が切れてしまうのではないかという恐怖心がある
・オフラインで会話していもスマホをチェックする など
これらの症状が「必要以上に強い」場合、依存傾向にあると言えるでしょう。
身体面にもたらす影響(例)
上記の症状の他に、スマホ依存には身体的・精神的にもさまざまな影響があるとされています。
代表的な症状として以下が挙げられます。
視力の低下
視力の低下はスマホだけが原因とは言えません。
しかし、スマホは長時間見続けることが多いため、視力の低下の一要因となっていることは事実です。
クロス・マーケティングが2023年に行った「目に関する調査」※によれば、全体の69%の人が眼精疲労を感じており、そのうちの4割が「スマホ依存」を自覚しているという結果となりました。
また若い年代ほど利用時間が長くなることから、スマホの過度な利用は視力の低下につながると考えられます。
ストレートネック
ストレートネックや猫背なども、スマホ利用による影響が大きいとされています。
スマホを見る際、前屈みになったり下を向いて見る方が多いのではないでしょうか。
こうした状況が長時間続いたり、頻繁に行われたりすると、本来S字を描く骨格が真っ直ぐになりストレートネックを引き起こします。
ストレートネックは肩こりや頭痛などの症状も引き起こすため、心当たりのある方は注意が必要です。
腱鞘炎(ドケルバン病)
いくらスマホが軽いとはいえ、長時間持ち続けることで手首に支障をきたします。
なかでも近年スマホの普及と共に問題となっているのが『ドケルバン病』という腱鞘炎です。
特に痛めた覚えもないのに、親指を広げたり、反らしたりする際に強い痛みがある場合は『ドケルバン病』の可能性があります※。
※公益社団法人|日本整形外科学会|ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)
精神面にもたらす影響(例)
精神面にもたらす代表的なものとしては、次のものがあります。
記憶力の低下
精神的な影響としては、記録力の低下が指摘されています。というのも、スマホから得られる情報があまりにも多いため、それにより脳が疲労を起こし、記憶力や集中力の低下が引き起こされようです。
さらに、寝る直前までスマホを見ることで睡眠リズムが崩れると、質の良い睡眠が取れなくなることもあるため、記憶力の低下につながると考えられています※。
コミュニケーション能力が下がる
SNSや動画視聴だけでは、コミュニケーション不足となることが否定できません。
確かにオンライン上やSNSで気軽にやり取りするのは可能ですが、それだけでは、コミュニケーション能力の低下につながる恐れがあります。
普段から相互的なコミュニケーションを取ることを心がけましょう。
脳疲労に注意
脳疲労とは、スマホなどの使いすぎにより脳が疲弊し、情報処理能力が低下する現象のことです。
症状としては、
・ミスが増える
・感情のコントロールがしにくくなる
・思考力や判断力の低下
などがあり、身体的にも
・頭痛
・不眠
・冷え性
・めまい
といった自律神経の乱れによる不調が生じます。
スマホ依存の解決のコツ

ここまで、スマホ依存がもたらす症状や影響について解説してきました。
スマホはあらゆる情報を手軽に入手できる反面、使いすぎには十分な注意が必要です。
また近年では、10代の若年層もスマホを持つ機会が増えたため、子どもにスマホを持たせる際には、親御さんの配慮も求められます。
セゾン自動車火災保険株式会社による、年代別のスマホ依存の実態調査※によれば、10代の93%以上が「気が付くとスマホに没頭し、時間を忘れている」状態にあり、16%が「一日中スマホを使用している」との結果が報告されました。
さらに子どもを持つ親の75.4%が「子供のスマホ使用に不安を抱えている」という結果に。
※セゾン自動車火災保険株式会社|10 代・20 代の約 9 割がスマホに没頭していると自覚!親子のスマホ使用時間に相関関係が見える驚きの結果に!
子どものスマホ依存を不安視している親も多いことから、できるだけスマホ以外にも目を向ける努力が必要となります。
そのためのコツとして、次のことを心がけてみてください。
スマホ以外の楽しさを見つける
スマホに依存してしまう原因として、家族や友人などとの現実生活におけるコミュニケーション不足が考えられます。
親しい人との交流が希薄になると、自分の内側に閉じこもりやすくなり、場合によっては自分が居場所ないと感じる場合いも考えられます。
そのため、スマホ以外に「楽器演奏」や「旅行」、「キャンプ」「料理を作る」など、別の楽しみを見つけることを心がけてみましょう。
自然に触れたり、新しい経験をしたりすれば、心と身体がリフレッシュされ、ストレス解消にもつながります。
少しずつスマホから離れる訓練をする
一日中お子さんがスマホを使っていたら、親として心配になるのは当然です。
つい頭ごなしに叱ってしまうかもしれませんが、そこはグッと堪えて「スモールステップ」を意識してみましょう。
例えば、ゲームに夢中になっているお子さんから、いきなりスマホを取り上げるのは逆効果となります。
使用するのを禁止するのではなく、「30分減らす」あるいは「すこしだけスマホから離れる時間を作る」
など、小さなことから始めてみてください。
ここで大切なのは「無理なく達成できる目標を設定すること」です。
小さな目標達成を積み重ねることが、スマホ依存の解決のコツです。
通知をミュートにする
可能な範囲で通知をミュートか完全にオフにすることを心がけてみましょう。
というのも、通知が来るたびに反応していては、仕事にも勉強にも支障がでます。
せっかく集中が高まっても、スマホの通知により中断されてしまっては台無しです。
「タスクを完成させるまでスマホを見ない」と決めて、通知をミュートにしすることを意識しましょう。
インターネット依存チェック
上述したように、現在のところスマホ依存は病気ではありません。
しかし、スマホ依存を扱うクリニックが増えているのも事実です。
「自分やお子さんの状態が心配」という方は、久里浜医療センターが作成したインターネット・チェックリストでご自身の状態を仮チェックしても良いかもしれません。
サイトへのリンクを貼りますので、心配な方は一度試してみてください。
久里浜医療センター
IAT:Internet Addiction Test(インターネット依存テスト)
スマホ依存まとめ
今回はスマホ依存の危険性や症状、解決のコツについて解説しました。
どれほど便利なものであっても、使い過ぎると問題が生じます。
スマホに翻弄されず、適切な用途や使用時間を意識しながら、日々の生活をより豊かなものにしていきましょう。
そして少しでも「大丈夫かな?」と不安に思ったら、遠慮せずに周囲に相談することをオススメします。
このブログでは教育やメンタルヘルス、支援制度などについて、さまざまな角度からアプローチしていますので、少しでも読者の皆様のお役に立てれば幸いです。
前回の記事はこちらから!(教育機会確保法について)



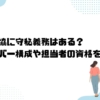
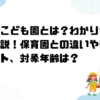

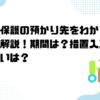
最近のコメント