ストレスチェック制度は意味がない?その背景や目的は?対象者、外部委託は可能?
この記事では、産業領域のカウンセリングの1つ「ストレスチェック制度」について解説します。
現在、常勤として会社勤めをされている方はもちろん、フリーランスの方やパートタイマーの方も含め、一度は実施した経験のある方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェックの実施は、従業員が十分なポテンシャルを発揮し、適切な人間関係を構築する上で欠かすことができない制度です。
その一方で、その実施については「意味がないのではないか」という声を聞くこともあります。
では、ストレスチェック制度とは具体的にどのような制度なのでしょうか。
今回はその目的や背景、対象者など幅広い観点からストレスチェック制度について見てみましょう。
本ブログの関連記事はこちら(EAP・従業員支援プログラム)。
ストレスチェック制度について

まずは、この制度について紹介します。
毎年受けてはいるものの、何となく受けているだけで、その背景や目的についてピンと来ていない方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェックとは?
現在多くの企業・団体で実施されているストレスチェック制度。
本制度は、従業員自身が心身の状態にいち早く気がつき、健全で安心な労働環境を整えるための制度です。
2015年12月より実施が義務化され、従業員はストレスに関連する質問表に答えることで、心身の状況を客観的に捉えることが可能となります。
一般に、法人・個人事業に関わらず、従業員50名以上の事業所に年1回の実施が義務付けられていますが、50人未満事業所については現在のところ努力義務が課せられています※。
※厚生労働省|労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要
また、ストレスチェックによりハイリスクであると判断された従業員は、医師や心理士といった専門家による面談も受けることができるため、健全な労働環境を作る上でも重要な制度と言えるでしょう。
なお、面談は従業員側の任意です。
背景について
ではストレスチェック制度が拡充される背景にはどのようなものがあるのでしょうか。
その大きな原因となっているのが、経済状況及び産業状況の急激な変化に伴う労働者の不安や悩み、ストレスの増加があります。
これまで労働環境の改善に関してさまざまな施策がとられてきたものの、「精神障害による労災認定件数」や「いじめ・嫌がらせに関する相談件数」は依然として増加傾向にあるのが現状です※。
参考:厚生労働省|令和元年度「過労死等の労災補償状況」を公表します
また、職場における離職者の問題についても依然として解決していない現状があります※。
※厚生労働省|離職率の推移
こうした状況を踏まえ、厚生労働省は「心の健康づくり計画の策定」として、新たに4つのメンタルヘルスケアの推進を掲げました※。ストレスチェックは、その中のセルフケアでおもに活用されており、従業員自身が早期にストレスに気が付くことに活用されています。
※厚生労働省|職場における心の健康づくり
4つのメンタルヘルスケアについてはEAP関連の記事で紹介していますので、
詳しくはそちらもお読みいただくと理解が深まります。
ストレスチェック制度の目的は?
念の為「4つのケア」とは以下の事項です。
1、セルフケア
▶️従業員に対してセルフケアが行えるよう、教育・研修を実施する
2、ラインによるケア
▶️従業員に状況への対応や復職支援など
3、事業場内産業保健スタッフ等によるケア
▶️事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが適切に実施されるよう、従業員及び管理監督者に対する支援を行う
4、事業場外資源によるケア
▶️、都道府県産業保健総合支援センターや医療機関など、事業所外のリソースを用いたケア
が掲げられています。
ストレスチェックの目的は多岐に渡りますが、大きく次の3つが挙げらるでしょう。
1、メンタルヘルスの不調を早期に防止
▶️上述の通り、依然として心身に大きなダメージを抱える従業員が後を断ちません。そのため、重大になる前に不調を把握し、早期の改善を目指します。
2、ストレス状況の確認
▶️不安や悩みを抱えていても、周囲に相談できない人も多いです。
そうした「周りには言えない」小さな変化をストレスチェックで確認します。
3、労働環境の改善や修復
▶️従業員にとって風通しの良い、働き安い環境を整えることも目的です。
たとえ「自分は大丈夫」と感じていても、「自分では気が付かない」潜在的なストレスを抱えているケースも多くあります。
小さなストレスから、潜在的なストレスを把握するのも、ストレスチェックの重要な目的です。
対象者は?
ストレスチェックの対象者についても紹介します。
基本的にその対象者は「企業・団体が常時雇用している従業員」です。
つまり、常時雇用者や直接雇用のパート・アルバイトも対象となります。
厚生労働省による、対象者の具体的な要件を見てみましょう。
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成28年4月改訂p30)には以下のように明記されています。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労
働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上で
ある者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されてい
る者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事
引用:厚生労働省|労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であるこ
と。
なお、1週間の労働時間が4分の3未満であっても、①の要件を満たし、かつ、1週間の労働時間数が
同種の業務に従事する通常の従業員の1週間の所定労働時間数のおよそ2分の1以上である労働者に対しても、ストレスチェックの実施が望まれています。
一方、役員や社長、派遣労働者は対象外ですが、派遣労働者は派遣元事業者がこれらを実施する必要があることは知っておくべきでしょう※。
※厚生労働省|労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルp112
ストレスチェックは意味がない?
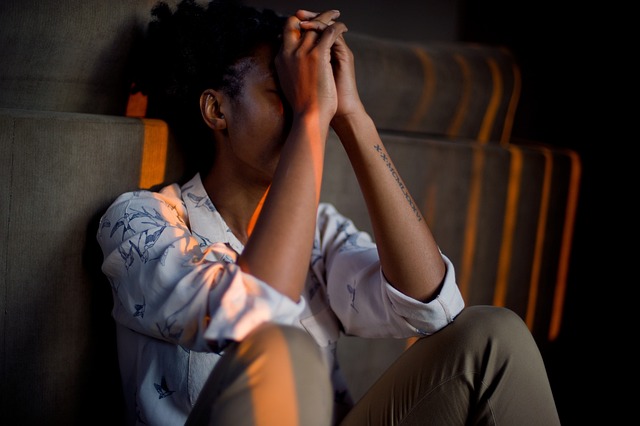
企業・団体の多くがストレスチェックを実施ししている一方で、中にはあまり意義を感じていない従業員も一定数いるようです。以下にその主な理由を紹介します。
意味がないと感じる理由①、結果を読むだけになっている
意味がないと感じる最大の原因として「結果を読むだけでそのままにしているから」が挙げられます。
また、実際に面談を行ったとしても「すでに自分でもわかっている」ことを言われるだけで、解決に結びつかないケースもあるようです。
確かにこれでは、意味がないと思うのも仕方ないかもしれません。
ストレスチェックを実施する企業・団体は多いながらも「受けるきまりだから受ける」という受け身の姿勢の方もまだまだ多いようです。
その②、従業員に受ける義務はない
ストレスチェック制度は企業・団体などの「事業場」に実施義務が課せられています。
したがって、そこで働く従業員に「受ける義務」はありません。
繁忙期であればチェックを断ることも、従業員の任意なわけです。
これでは「意味がない」と思う従業員も出てくることも考えられます。
しかし、ストレスチェックは受検者の心身の状態のほかにも、職場環境や人間関係を改善する大切な機会でもあります。
そのため、可能な限り実施に参加してみましょう。
日頃の小さな気づきを伝えてみるだけでも、新しい視点が得られるかもしれません。
その③、結果を職場に活かせていない
意味がないと感じる理由の3つ目として「職場にフィードバックされていない」が挙げます。
事実、ストレスチェックを実施したところで「職場環境が改善されていない」と感じる方も多いことでしょう。
しかし、平成27年度からの開始以降、ストレスチェック制度を実施する企業の割合は8割に上り、令和4年の労働安全衛生調査によれば、集団ごとの分析を実施した事業所の72.2%のうち、80.2%が分析結果を活用しています※。
もちろん、まだまだ改善の余地は無数に残されていますが、着実に広がりつつあることも事実です。
※厚生労働省|令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況p5
ストレスチェック制度は外部委託もできる

年に1度の実施義務があるストレスチェック制度。
しかし、すべての事業所において対応できるとはかぎりません。
なかには、繁忙期などで準備できないケースや、担当者が実施できないケースもあることでしょう
そういう場合はには、ストレスチェックを外部委託することも可能です。
これは上記「4つのケア」のうちの4番目「事業場外資源によるケア」に該当します。
ストレスチェックを外部に委託すれば、事業者の準備も不要になるだけでなく、データ管理や面談の手配、
集団分析などトータルでサポートが受けられので、継続が難しいと考える事業者に非常に有益です。
さらに、外部委託することで事業内に個人情報が漏れる心配も格段に低くなるため、ストレスチェックの正確性が高まることも期待できます。
その一方で、外部に委託する場合はサポートの範囲によりコストが変わることがあるため、金銭面での折り合いが必要となることは注意が必要です。
なお、ストレスチェックは以下の資格を持った人が実施します。
・医師
・保健師
・精神保険福祉士
・看護師
・歯科医師
・公認心理師
ただし、精神保険福祉士、看護師、歯科医師、公認心理師の4資格については、
厚生労働大臣が定める研修を修了する必要があります。
ストレスチェック制度まとめ
ストレスチェック制度について解説しました。
労働環境の改善には依然として多くの課題があるものの、徐々に実施割合や分析結果をフィードバックする事業所が増えています。
より良い職場環境、そしてポテンシャルを十分に発揮するためにも、積極的にストレスチェック制度を取り入れてみてるのも良いかもしれません。







最近のコメント