社会復帰施設(未成年)にはどんなところがある?施設ごとの役割や違いは?加害者支援は必要?
この記事では、おもに少年に対する社会復帰施設について紹介します。
加害者に対して、ネガティブな印象を持つ人が圧倒的であるのは当然のことです。
しかし、罪を犯した少年たちが、どのような施設に入り、どういった活動をしているのかを知るのも、大切なことではないでしょうか。
現在の日本では、少年の社会復帰を促す施設として、少年鑑別所、少年院、少年刑務所の3つが設置されています。
とはいえ、これらの違いをきちんと理解している方は少ないはずです。
そこで以下では、これら3つの施設について、その役割を解説しながら、加害者支援の意味についても考えてみたいと思います。
前回のEAP(従業員支援プログラム)についてはコチラ!
社会復帰施設について

少年の社会復帰を目的とした施設には、少年鑑別所、少年院、少年刑務所の3つがあると冒頭でお伝えしました。以下では、それぞれの役割や活動について解説します。
社会復帰施設1・少年鑑別所
全国に52ヶ所設置※されている、法務省管轄の少年を鑑別するための施設です。
しばしば、少年院と混同されますが、少年鑑別所は、少年審判の必要性を判断するための施設であるため、厳しい処遇や課題を課せられことはありません。
少年鑑別所の主な目的として、以下の3つが挙げられます※。
1、家庭裁判所等の求めに応じ、鑑別を行うこと
2、観護の措置の決定が執られて収容している者等に対して、観護処遇を行うこと
3、地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと
※法務省|全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧
※法務省矯正局|少年鑑別所のしおり
鑑別について
鑑別は家庭裁判所の求めに応じて行われるもので、観護措置により収容された少年に実施されます。
鑑別と聞くと、厳しい取り締まりを想像する人も多いのではないでしょうか。
しかし、少年鑑別所で実施される鑑別とは、
医学や心理学、教育学、社会学といった専門的な知識や技術に基づきながら、
対象者の本来的な資質や、環境上問題となる事案を明らかにすることです。
また対象者が抱える事情を改善し、適切な指針を示すことも鑑別の重要な役割となっています。
鑑別には、
1、収容鑑別
2、在宅鑑別
3、依頼鑑別
4、一般鑑別
の4種類があり、
専門家による面談や行動観察、知能検査など、さまざまな角度から鑑別が行われます。
観護措置期間は?
観護措置とは、非行を行なった少年に対して家庭裁判所が下す処遇の1つです。
収容期間はおよそ4週間が一般的ですが、家庭裁判所の判断により、最長8週間まで延長されるケースもあります。
収容期間中は、少年によっては教科書を使っての学習など、学校の授業に遅れが出ないよう配慮されるケースもある他、スポーツや読書の時間も設けられています。
観護措置=少年鑑別所の収容
という図式がわかりやすいかもしれません。
社会復帰施設2・少年院
家庭裁判所により、保護処分が妥当とされた少年が収容される施設です。
保護処分とは、保護観察・少年院送致・児童自立支援施設等送致によって、更生を図るための処分のことを言います。
現在、日本では48ヶ所設置されており、こちらも少年鑑別所と同じく法務省の管轄です。
少年院はおよそ12歳から20歳までの少年を収容しており、犯罪の頻度や心身の障害の重症度に応じて、少年院法第4条により、第1種から第5種まで設けられています※。
※少年院法第4条(少年院の種類)
家庭裁判所により、保護処分が妥当とされた少年が収容される施設です。
少年院で実施される矯正教育は、おもに以下の3つです※。
1、矯正教育課程
👉在院者の共通する特性ごとに重点的に実施する矯正教育の内容や期間を定めた標準的なコースであり、少年院ごとに指定されています。
2、少年院矯正教育課程
👉各少年院が指定された矯正教育課程ごとに、施設の立地や地域からの支援などを活かして定めるカリキュラムです。
3、個人別矯正教育計画
👉在院者一人ひとりの特性に応じた矯正教育の目標、内容、期間や実施方法を具体的に定めたものであり、この計画に基づき、きめ細かい教育が実施されます。
少年院での生活は?
犯した罪に向き合い、改善措置や社会復帰を目指すことが少年院の目的です。
そのため、少年院では在院者の性質や資質ごとに1日のプログラムが課せられます。
少年院での生活モデルを以下に見てみましょう※。
- 06:30 起床
- 07:40 朝食・自主学習
- 08:50 朝礼
- 09:00 生活指導・職業指導・強化指導等
- 12:00 昼食・余暇
- 13:00 生活指導・職業指導・強化指導等
- 17:00 夕食・役割活動
- 18:00 集団討議・教養講座・個別面接等
- 20:00 余暇
- 21:00 就寝
※参照:法務省矯正局|明日につなぐ|少年院のしおりの図を元に作成
そのほか、障害等により自立が困難な場合は、地域生活定着支援センター等と連携し、生活先の確保も行なっています。
少年鑑別所との違い
少年鑑別所と少年院を同じものと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、両者の役割はまったく異なります。
少年院は、家庭裁判所の判決により「矯正が必要」と判断されたケースに、少年が収容される施設です。
そのため、少年院では矯正教育や矯正指導・職業訓練が課せられます。
一方、少年鑑別所は前述の通り、少年を「鑑別する」施設であるため、
矯正教育や職業訓練などは課せられません。
社会復帰施設3・少年刑務所
少年刑務所とは、16歳以上20歳未満の刑事裁判で実刑判決を受けた少年を収容する施設であり、現在、日本では6つの少年刑務所が設置されています。
少年鑑別所や少年院とは異なり、少年刑務所では受刑者への刑罰が執行され、収容事例もさまざまです。
たとえば、以下のようなケースが収容事例として挙げられます。
- 少年院などの保護処分では更生が見られない場合(複数回繰り返し罪を犯すなど)
- 16歳以上の少年が、故意に犯罪行為を行い、人を死亡させた場合
- 強盗や放火など、懲役・禁錮刑の下限が1年以上の罪を犯した場合
など
収容期間
少年であることから、それぞれの年代に応じた配慮や処遇が行われるものの、懲役刑の判決が下されているため、収容期間中は刑務作業が課せられます。
1日の刑務時間は平日8時間。
そのほか改善に向けた指導や教科指導も併せて実施されます。
収容期間は裁判結果により異なりますが、5年を超えるような長期にわたるケースが多いようです。
また、少年とはいえ、刑事裁判によって実刑判決が言い渡されているため、受刑者には「前科」がつきます。
加害者支援の意味を考える
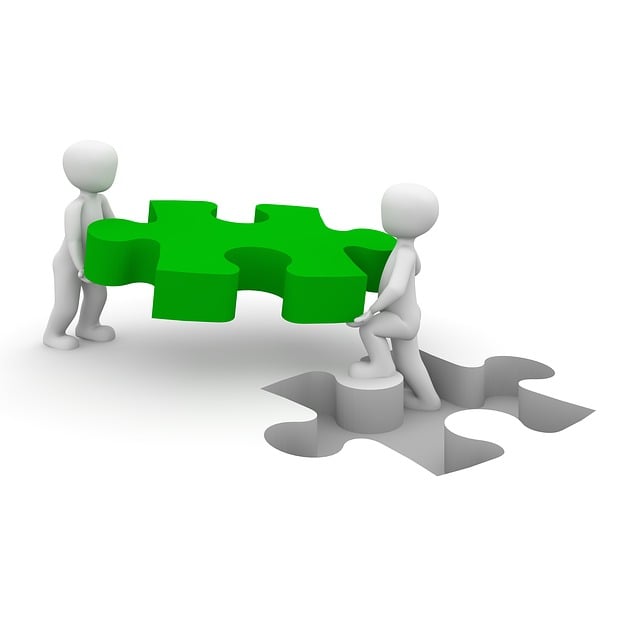
ここまで、少年に対する社会復帰施設について紹介しました。
少年であれ成人であれ、犯罪を犯した際には社会的な制裁を受けなければなりません。
そして何よりも、被害者本人、そしてその家族の苦痛が少しでも軽減される世の中であるべきです。
2005年4月から、犯罪被害者等基本法が施行され※、
・相談及び情報の提供等
・給付金の支給に係る制度の充実等
・安全の確保
・居住の安定
といった施策が定められました。
※警察庁|犯罪被害者等基本法
この法律によって、すべての被害者が救われるわけではありませんが、支援の大枠としての目処はたったようです。
加害者支援も考える必要がある
一方、加害者の家族をサポートする体制は、未だ皆無に近い状態であるのをご存じでしょうか。
もちろん、
・「加害者やその家族に手を差し伸べる必要なんてない!」
・「犯罪を犯した人間が100%悪いに決まっている」
・「その家族も同罪」
・「被害者や家族の気持ちを考えたら、加害者やその家族のサポートなんて不謹慎だ」
といった言葉が返ってくるのは承知しています。
しかし、被害者の家族と加害者(家族含む)の末路は、驚くほど似ているとも言われています※。
とするならば、加害者支援を社会問題として考えることも、今後は重要な課題になるかもしれません。
※公益財団法人|東京都人権啓発センター|加害者家族支援への道のり負の連鎖を断ち切るために
まとめ
今回は、社会復帰施設(未成年)について紹介しました。
名称が似ているため混同しがちですが、それぞれの施設ごとの役割を、ざっくりとご理解いただけたと思います。
このブログでは、学校臨床や教育制度、支援施策なとについて網羅的に解説しています。
他の記事もお読みいただくと、理解がより一層深まりますので、併せてご一読ください。
コチラの記事(高校無償化)も人気です!






最近のコメント