PFA(サイコロジカル・ファーストエイド)とは?資格がなくてもできる?目的や注意点、ポイントを簡単に解説!(学校版もあり)
PFA(サイコロジカル・ファーストエイド)は、
災害に被災した方や犯罪に巻き込まれた方に対して行う直近の処置のことを言います。
日本語では「心理的応急措置」と呼ばれており、専門知識や資格などがなくても、誰でも取り組める身近な支援として、近年注目を集めています。
とはいえ、PFAという言葉を初めて聞いた方も多いことでしょう。
そこで本記事では、その目的や注意点、ポイントについて簡単に紹介します。
一人ひとりの力は小さいかもしれません。
しかし、理解者が増えればその力は大きなものになるはずです。
前回の記事ではEAP(従業員支援プログラム)について解説しています。
さまざまな支援について知りたい方はそちらも併せてご一読ください。
PFA(サイコロジカル・ファーストエイド)とは?

身近な人々に対し、自分ができることの範囲内で手を差し伸べるのがPFAの基本理念です。
そのため、誰もが実践でき、年齢・性別・人種・国籍による対象者も限定されません。
以下ではPFAについてわかりやすく紹介します。
基本理念について
PFAとは、災害による被災者の方や、事件・事故などに巻き込まれた方に提供する「心理的支援のマニュアル」のことを言います。
もともとは、アメリカ国立PTSDセンターと、アメリカ国立子どもトラウマティックストレス·ネットワークによって開発されました。
またPFAという言葉自体は1950年代頃から使用されており、それほど新しい理念ではありません。
現在ではWHO(世界保健機構)が作成したマニュアルが普及し、苦しむ人々に手を差し伸べる1つの指針として、世界中で活用されています。
日本においても厚生労働省がPFAのマニュアル(翻訳版)を公開しており※、徐々にその認知も高まりつつまるようです。
※厚生労働省|心理的応急措置サイコロジカル·ファーストエイド)
「心理的」という言葉から、カウンセリングに特化したマニュアルと思う方もいるかもしれません。
しかしPFAは心理面だけでなく、社会的生活を支える支援も含まれているのも大きな特徴です。
なお、アメリカ国立PTSDセンターと、アメリカ国立子どもトラウマティックストレス·ネットワークによって開発されたものは、アメリカ版として普及しています。
日本では,兵庫県こころのケアセンター※によって訳されています。
※兵庫県こころのケアセンター|「サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き 第2版」日本語版
目的は?
災害や戦争、事故や事件に遭遇した人の中には、心身に多大なストレスを抱えることも少なくありません。
PFAはそうした人々に対し、身体的・心理的・物質において安心できる環境づくりを支援し、それ以上の危害を受けないよう守ることを目的としています。
そのほか、PFAの目的は多岐にわたり、「サイコロジカル・ファーストエイド」実施の手続き第2版では、
以下のことが主な目的として明記されています。
サイコロジカル・ファーストエイドの基本目的
Basic Objectives of Psychological First Aid
・被災者に負担をかけない共感的な態度によって、人と人の関係を結びます。・当面の安全を確かなものにし、被災者が物心両面において安心できるようにします。
・情緒的に圧倒され、取り乱している被災者を落ちつかせ、見通しがもてるようにします。
・いまどうしてほしいのか、何が気がかりなのか、被災者が支援者に明確に伝えられるように手助けします。また、必要に応じて周辺情報を集めます。
・被災者がいま必要としていることや、気がかりなことを解決できるように、現実的な支援と情報を提供します。
・被災者を、家族、友人、近隣、地域支援などのソーシャルサポート・ネットワークに、可能な限り早く結びつけま
す。・適切な対処行動を支持し、その努力と効果を認めることで、被災者のもっている力を引き出し、育てます。そのために、大人、子ども、家族全体がそれぞれ、回復過程で積極的な役割を果たせるよう支援します。
・災害の心理的衝撃に効果的に対処するために役に立つ情報を提供します。
・支援者ができることとできないことを明らかにし、(必要なときには)被災者を他の支援チーム、地域の支援システム、精神保健福祉サービス、公的機関などに紹介します
引用:サイコロジカル・ファーストエイド 実施の手続き第2版|サイコロジカル・ファーストエイドの基本目的
PFAは専門家でなくてもできる
心理的・社会的ケアと聞くと、専門的知識が必要と思う方もいるかもしれません。
しかしPFAは医師や心理師などが行うカウンセリングとは異なり、必ずしも専門的知識を必要としません。
そのため消防や学校、警察、行政、産業といった一般的な職業から、ボランティアなども該当します。
PFAを実施する上で重要なのは、被災者や被害者本人が自発的に話したい場合、
あるいは支援が必要であると訴える場合に限り支援し、コミュニケーションを促進しながら、心理的連携を図ることにあります。
PFAを行う際の注意点やポイント
支援者がPFAを行う際には、注意点やポイントがあります。
上述した通り、PFAは支援を必要としている人に対し行うことが重要です。
以下に注意点やポイントをまとめました※。
1、支援に入る土地や文化、礼儀を尊重し自分の立ち位置をわきまえる
2、支援活動をする人や団体、組織の営利のためにPFAを用いない
3、支援を望んでいない人に援助の申し出をしない
4、PFAの対象者となるのは、ごく最近に危機的状況に陥った人々であること
5、対象者が重篤の場合、または他者へ危害を及ぼす可能性がある場合は対処はしない(専門家につなぐ)
6、無理に話を引き出そうとしない(でしゃばらない)
など。
1、安全、尊厳、権利を尊重する
👉自分の行動が相手の苦にならないように配慮する
2、相手の文化に配慮し、それに従うこと
👉衣服、言語、年齢、性別、力関係、身体に触れること、振る舞い、信念、宗教など
3、そのほかの緊急対応策を把握する
👉大規模災害を支援する際には、当局の指示に従う
👉自分の行動範囲・支援範囲をきちんと理解する
4、自分自分のケアを行う
👉自分の心身の状態を整えること
※参考|厚生労働省|心理的応急処置(サイコロジカル·ファーストエイド)|第2章 責任ある支援
PFAには学校版もある
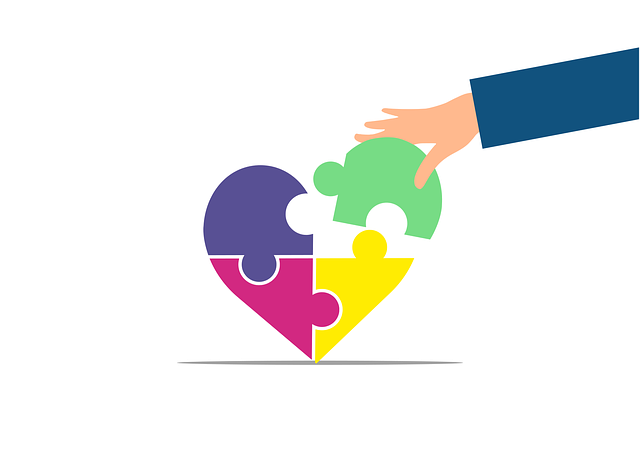
ここまで、PFAの基本理念や目的、ポイントについて解説してきました。
PFAマニュアルは、PFA-S(サイコロジカル·ファーストエイド学校版)としてもモデル化されています。
簡単に紹介してみましょう。
PFA-S(サイコロジカル·ファーストエイド学校版)について
PFAは世界に共通する支援マニュアルですが、その学校版としてPFA-S(Psychological First Aid for School)にも応用されています。
PFA-Sは、学校における非常事態に対応した支援マニュアルであり、生徒はもちろん、その家族や教職員、学校側に適応されます。
PFAと同様に、非常時における初期の苦痛や混乱を軽減することや、短期・長期を問わず、適応機能や対処行動を促すことを目的としたものです。
そのほか、以下の目的が考慮されています。
・負担をかけない共感的な態度によって、生徒や教職員と良い関係を作ります。
・当面の安全を確かなものにし、被災者が心身両面において安心できるようにします。
・情緒的に圧倒され、取り乱している生徒や教職員を落ち着かせ、見通しが持てるようにします。
・今どうしてほしいのか、何が気がかりなのか、生徒や教職員が気付けるように手助けをします。
・生徒や教職員が今必要としていることや、気がかりなことを解決できるように、現実的な支援と情報を提供します。
・生徒や教職員を、家族、友人、コーチ、その他学校や地域のグループなどのソーシャルサポートネットワークに、可能な限り早く結び付けます。
・生徒、教職員、家族の強さと対処行動に敬意を払い、回復においては彼らが能動的な役割を果たせるように勇気付け、適切的な対処行動を引き出します。
・支援者ができることとできないことを明らかにし、(必要なときには)生徒や教職員に、スクールカウンセラー、ピアサポートプログラム、放課後活動、家庭教師、プライマリケアの医療機関、地域の支援システム、精神保健福祉サービス、従業員援助プログラム、公的機関、その他の援助機関などを紹介します。
引用:サイコロジカル・ファーストエイド学校版実施の手引き|PFA-S 提供者の基本目的とは?
注意点
基本理念はPFAと同じですが、学校版では事前に学校のことを知り、起きた出来事の特徴を知ることも重要です。
学校で援助を提供する際には、以下の点に注意する必要があります。
・どこで発生したのか(事件や事故など)
・いつ発生したのか、あるいはどれくらい続いたのか
・出来事の規模(屋内か屋外か)
・特筆すべき特徴はあるか(殺人事件、テロなど)
いずれにしても、高リスクにさらされた人を見極め、PFAと同様に「求められ、必要に応じて」支援することを心がけてください。
PFAの解説まとめ
今回はPFAについて、その理念や注意点、目的を紹介しました。
一人ひとりの理解が、非常時において大きな力となります。
これまでPFAをご存じなかった方にとって、この記事が「自分に何ができるのか」と改めて考えるきっかけになれば幸いです。
PFAについてより詳細に知りたい方は、記事内リンクをクリックしていただくと、参考元リーフレットをご覧いただけます。






最近のコメント