適応指導教室(教育支援センター)とは。目的や役割、フリースクールとの違いは?申請方法や利用条件を簡単に解説します
適応指導教室(教育支援センター)について紹介します。
昨今、小・中学生における不登校の割合が、急激な増加傾向にあることをご存知でしょうか。
文部科学省が令和5年に発表した資料※によれば、令和4年度における小・中学生の不登校総数は299.048人となり、30万人に迫る勢いです。
※文部科学省|令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要p20
不登校の要因はいくつもあり、いじめや勉強不振といった学校に関わるものから、家庭の状況、本人の状況などさまざまです。
しかしどのような原因であれ、長期に及ぶ不登校は児童・生徒の学習の機会を奪うものであり、教育の均等性を大きく損なう恐れがあります。
そのような状況の中、不登校児童・生徒への教育機会を充実させるため、適応指導教室(教育支援センター)の役割が注目されています。
適応指導教室(教育支援センター)とは

学校に通えない児童・生徒の教育支援として、重要な役割を担っている適応指導教室。
親御さんの中には、教育支援センターという名称で聞いたことがある方も多いと思います。
しかし「どのような支援を受けられるのか」「費用がかかるのか」など、疑問に思われる方もいることでしょう。
どのような支援を受けられる?
適応指導教室(教育支援センター)とは、不登校により学校に通えない児童・生徒のために、教育センターなど学校以外の施設や、学校の余裕教室などで学習を支援するものです。
またこれまでは主に学校復帰を最終目標としていましたが、教育機会確保法の制定以降は、児童・生徒の社会的な自立を促す目的へシフトしつつあります。
支援では、
・集団生活への適応や心の安定を図る
・基礎的学力の向上
・生活改善のための指導
などが行われています。
指導にあたっては、教員免許保持者や臨床心理士、社会福祉士といった、専門スキルを有する職員が配置されるため、一人ひとりの子どもの状況に合わせた支援が受けられるのが特徴です。
さらに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった、学校臨床の専門家が配置されるケースも少なくありません。
指導員には、年齢や職業等を問わずさまざまな人材が採用されており、多様な人材と接することで、児童・生徒の社会復帰にも大きな役割を果たしています。
校内適応指導教室が実施されるケースも
適応指導教室(教育支援センター)は、子どもが通う学校とは別に配置されているのが一般的です。
しかし中には、通学する学校内で実施されている場合もあり、登校が難しい生徒への支援の場として活用されています。
たとえば、再登校の前段階として、別室に登校することで再登校を促すよう利用されたり、学校生活や授業に適応するための練習の場として、当該の学校が使用されたりするケースもあります。
校内適応指導教室では、登校時間や校内活動のスケジュールが調整可能で、児童・生徒に配慮した支援が行われています。
モデルケースとして以下をご参照ください。
・登校時刻をずらし、他の生徒に会わないようにする
・登校時刻を記入する
・1日の過ごし方を設定する
・時間に合わせて自習学習を行う
・学校行事や帰りの会等は参加できる範囲で参加する
・定期的なカウンセリングの実施 など
参考|校内適応指導教室
現在は一部の学校でのみ実施されていますが、文部科学省や東京都などが積極的に推進しているため、今後は校内適応指導教室の拡大が期待されます※1。
また文部科学省が発表した「教育支援センター整備指針(試案)」※2によれば、今後さらに支援機能が拡充する予定です。
※1日本教育新聞|校内支援センター設置拡大を 不登校対応で報告書
目的や役割は?
上述した通り適応指導教室(教育支援センター)の目的は、不登校に悩む児童・生徒の社会復帰を促すための支援です。
またこれに加えて、行き場のない児童・生徒に対する居場所の提供も大きな役割と言えるでしょう。
相談員やカウンセラーなどとコミュニケーションをはかりながら、環境適応の練習や学習指導を受けることで不登校を克服し、学校に戻ることが大きな目標です。
また近年では、教育機会確保法の改正により、センターの整備に関する新しい指針が示されています。
整備の進み具合は自治体ごとに異なるものの、今後は「社会的な自立を目指す」ことや「訪問相談・支援」などが強化される予定です。
なお、支援内容は大きく次の3つに分けられます。
学習支援
適応指導教室におけるもっともスタンダードな取り組みが学習支援です。
指導は個別で行われることが多く、カリキュラム通りに学習を進める教室や、自習をメインとする教室などさまざまです。
教材についても、学校の教科書を使用する場合や、市販の問題集を付属的に用いることもあります。
不登校になると学習の機会が著しく低減するのが一般的です。
しかし、適応指導教室(教育支援センター)を利用することで、カリキュラムに沿った学習を進めることが可能となります。
他者とのコミュニケーションの場として
学習支援の他に重要な役割に、コミュニケーションの機会の提供が挙げらます。
そのため、支援ではグループでのスポーツやレク、芸術活動や野外活動などを通じて、コミュニケーションの練習が行われることも多いようです。
自分一人だけでなく「仲間と共に行動する」「協力する」経験を通じて、児童・生徒の自主性や社会性を養うことを目的としています。
心の健康相談(カウンセリング)
不登校の原因は児童・生徒により異なります。
そのため、状況に応じたカウンセリングも重要なサポートの1つです。定期的なカウンセリングの実施は、児童・生徒の心の変化の理解にもつながり、社会復帰を促すことのサポートとなります。
また、児童・生徒だけでなく保護者もカウンセリングを受けられる場合もあり、積極的に活用することをオススメします。
適応指導教室(教育支援センター)と教育相談室を併設している自治体も多くありますので、教育相談室でカウンセリングを受けながらの通室も可能です。
適応指導教室とフリースクールの違いは?

学習支援の場として、フリースクールを思い浮かべる方もいらっしゃると思います。
しかし適応指導教室とフリースクールでは、運営方法や指導方針の点で大きく異なります。
以下ではその違いについて見てみましょう。
フリースクールとは
フリースクールとは個人や企業、NPO法人などの団体によって運営されている学習支援施設です。
適応指導教室では文部科学省による要件が記されています。
一方、フリースクールの場合は、支援方針や学習支援を運営側が決めるため、
それぞれの団体ごとに支援内容が異なります。
また適応指導教室では、対象者が児童・生徒(高校生を含むケースも有り)が一般的ですが、フリースクールでは社会人も通える団体もあるのが特徴です。
公的施設である適応指導教室は無料で利用できますが、フリースクールでは費用が発生する点も押さえておきましょう。費用は施設ごとにことなりますので、利用前にきちんと確認することが大切です。
費用の有無
上記の通り費用については、
・適応指導教室は基本無料
・フリースクールは有料
と覚えておきましょう。
この点についてもう少し詳しく紹介します。
文部科学省による報告※によれば、フリースクールの授業料の平均額は約3万3000円、団体・施設のおよそ3割が入会金を1〜3万に設定しているようです。
さらに、フリースクール全体としてみた入会金の平均額は約5万3000円という結果となりました。
しかしなかには入会金が10万円を超える団体もあるようなので、利用の際には、施設や支援内容を十分に確認してから申し込みましょう。
※文部科学省|小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査
適応指導教室は出席扱いになる
出欠席についても違いがあります。
適応指導教室は各自治体によって運営されています。
そのため多くの場合、学校の出席と同等に扱われます。
また、これまでは学校への復帰を前提としていましたが、今後は社会的自立を目指すほか、児童・生徒本人の登校希望の有無に関わらず(登校意思の有無に関わらず)支援対象となります(これまでも意思を示せない児童生徒に対する支援は多々ありましたが)。
しかしフリースクールの場合は出席とみなされないケースがほとんどです。
フリースクールが出席とみなされるかどうかは、学校長の判断による場合があるため、に相談する必要があるでしょう。
以下では、適応指導教室を実施している自治体(例)を紹介します。
1.東京都板橋区板橋フレンドセンター
不登校で悩む児童・生徒、家族のための相談(電話も可)や、自習学習支援、体験活動の実施。
費用:無料
2.大阪府大阪市教育支援センター
不登校児童・生徒への学習支援、教育相談。
心理カウンセラーによる面談も有り。
さらに支援として、大阪市内の小中学校の巡回も実施。
大阪市|不登校児童生徒支援のための大阪市教育支援センターについて
3、埼玉県川口市教育相談
埼玉県川口市では、川口市立教育研究所を拠点として、さまざまな相談に対応しています。
・電話相談
・子ども教育相談
・学校巡回教育相談
また、小中学生を対象とした適応指導教室「オンラインわくわく・チャレンジ」では、
令和4年4月よりGIGAスクール端末を用いた教育支援が実施されています。
GIGAスクール構想についてはこちらに書いています。
申請方法や利用条件について
申請方法や利用条件について気になる方もいるでしょう。
方法や条件は、各自治体ごとに基準が異なります。
したがって、ご利用を希望する際は、お住まいの自治体ホームページから確認してください。
たとえば「〇〇市 適応指導教室」や「〇〇市 教育支援センター」で検索すると、
確認できます。
そして利用を検討する際は、
「お子さん本人が本当に通いたいかどうか」を確認することも大切です。
お子さんによっては、適応指導教室に合わないケースも考えられます。
「学校に行けない=適応指導教室」では、お子さんの心に負担がかかる場合もあるかもしれません。
そのため、無理に勧めることはなるべく控えて(気持ちはわかりますが)、学習支援方針や指導員の人柄、施設の雰囲気等などをよく見た上で、お子さんの気持ちに配慮しながら、選択肢の1つとして考えると良いでしょう。
適応指導教室(教育支援センター)まとめ
今回は適応指導教室について紹介しました。
不登校児童・生徒が急増する昨今、お子さんとの接し方について悩まれている方も多いと思います。
しかし、相談できる場所は意外に身近なところにあるものです。
また、自治体ごとにさまざまな支援も実施されています。
お子さんの不登校や生活習慣などで不安を抱えている親御さんがおられましたら、
遠慮せず、ぜひ最寄りの適応指導教室に相談してみてください。



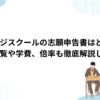



最近のコメント