教育機会確保法を簡単に解説!その理念や問題点、現状や教育施設も紹介!
教育機会確保法についてわかりやすく解説しています。
小・中学校生のお子さんを持つ親御さんなら、学校からの通知等で一度は聞いたことがあるかもしれません。
しかし実際には「そんな法律聞いたことない」や、「聞いたことはあるけど、実際どんなものなの?」
と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、教育機会確保法の概論や理念を説明しながら、親御さんが利用できる教育施設も解説していきます。後半では施設に関する具体的な問い合わせ先も紹介しますので、ご利用を検討する際のご一助になれば幸いです。
教育機会確保法とは?
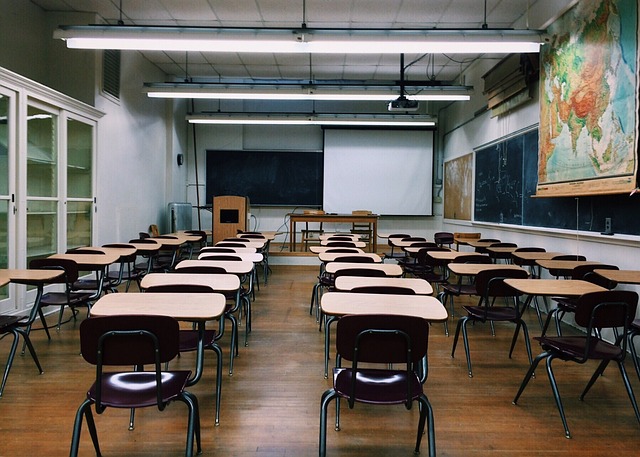
法律名だけ聞いても、あまりピンとこない方も多いと思います。
教育機会確保法とは、児童や生徒一人ひとりに合わせた学びの場を保証する法律です。
2017年から新たに施行され、何らかの理由により学校に行けない児童・生徒を積極的にサポートする取り組みとして、現在徐々に広がりを見せています。
この法律が制定されるに至った大きな背景として、児童・生徒の不登校の増加が挙げられます。
児童・生徒の不登校数は近年急激な増加傾向にあり、文部科学省が行った調査によれば※、令和4年度の小中学生の不登校児数は、299,048人と過去最高に達しており、非常に深刻な状況に直面しているのが現状です。
これは小学生の77人に1人、中学生の20人に1人が不登校という計算となり、教育機会確保法の適用が今後ますます増加していくことが予測されます。
※文部科学省|令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要p19~20
教育機会確保法の理念について
こうした問題を解決するために、教育機会確保法では5つの理念が掲げられています。
1、全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
2、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支
3、不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
4、義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
5、国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携 国の責務、地方公共団体の責務、財政上の措置等について規定
引用|文部科学省|義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要)
またこれらを達成する取り組みとして、主に以下のことが課題となっています。
・いじめ、仲間はずれのない環境づくり
・GIGAスクール構想におけるICTを活用した援助
・夜間中学の設置
・教育機会を提供する民間団体との連携(フリースクールなど)
・登校できない児童・生徒に対する居場所の提供
・不登校特例校の設置
など。
日本においては教育基本法などにより、国民が等しく教育を受ける権利が保証されています。
そのため、現状に合わせた柔軟な取り組みが今後の大きな課題と言えるでしょう。
教育機会確保法の問題点や現状は?

児童・生徒を支援するさまざま施作が行われている一方で、問題点も考えなければなりません。
本法律が施行されて以来、次のような問題が浮き彫りとなりました。
教員の負担が増す
教育機会確保法では、児童・生徒に対するさらなる対応が求められます。
例えば教員による、不登校児・生徒への家庭訪問や現状把握はより一層強化されなければなりません。
そのため、ただでさえ激務に追われる教員の負担がこれまで以上に増すことが懸念されます。
加えて、GIGAスクール構想によるICTの操作など、あらたな業務が求められているのが現状も無視できません。
1人の教員が担当する業務には限度があることから、業務が分担できる改革・制度が必要となるでしょう。
GIGAスクール構想についてはコチラをご一読ください。
フリースクール不足
登校できない児童・生徒にとって、そして親御さんにとってもフリースクールの存在は欠かせません。
相談やカウンセリング、個別学習に対応するフリースクールは、安心して預けられる反面、全体的な数の少なさが課題となっています。
また地方においては、フリースクールがあったとしても、アクセスが悪かったりと、通いたくても通えないという状況もあるようです。
そのため、フリースクールに通いやすい環境整備や、新たな設置などが今後の課題として挙げられます。
不登校への理解促進
教育機会確保法が施行以降、保護者の方も耳にされる機会が増えたのではないでしょうか。
上記の通り、不登校は増加傾向にあるものの、それに対する周囲の理解が追いついてないのが現状です。
不登校にはさまざまな理由があり、児童・生徒一人ひとり原因が異なります。
そのため、学校側と保護者の双方に不登校への理解が求められています。
親としては周囲の児童・生徒と同じように、自分の子供にも学校に行って欲しい気持ちがあるとは思いますが、そのことが余計に子供を追い詰めることも少なくありません。
保護者だけでなく、地域社会全体における理解が大きな課題となっています。
夜間中学の設置が進まない
教育機会確保法の施行に伴い、夜間中学の設置が急がれています。
これについて、現在国はすべての都道府県に最低でも1つの設置を推進しているものの、
なかなか達成には至っていません。
文部科学省が発表した調査によると、令和5年10月現在、17都道府県に44校が設置されていますが、
目標までかなりの時間とハードルがあるようです※。
夜間中学には、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの配置も必要なため、人材の確保も大きな課題と言えるでしょう。
※文部科学省|夜間中学の設置促進・充実について|夜間中学の設置・検討状況
学校以外の学びの施設

教育機会確保法では、学校だけが学びの場ではありません。
学校以外にも多くの学びの場があり、以下では代表的なものを4つ紹介します。
教育支援センター(適応指導教室)
1つ目は教育支援センター(適応指導教室)です。
この施設は各市区町村などの教育委員会が運営しており、主に不登校の生徒向けに開かれています。
基本的に無料で利用可能です。
受け入れ対象は小学生から高校生、高校中退までと幅広く※、不登校を克服し、学校に戻る社会復帰の手助けが目的です。
また適応指導員には元教師、臨床心理士などが担当しているため、日々のカウンセリングや交流の場としても利用されています。
そのほか、親に対する支援にも取り組んでおり、親同士のつながりが持てるのも特徴です。
※文部科学省|「教育支援センター(適応指導教室) に関する実態調査」結果p7
フリースクール
フリースクールとは、さまざまな理由で学校に行けない生徒の居場所を提供する場所です。対象年齢も小学生・中学生・高校生と幅広く、発達障害や身体的障害、知的障害などを抱える生徒も受け入れています。
個人で経営する人やNPO法人、ボランティア団体など、民間で運営されており、教育方針も団体により異なります。
学校における教育課程のように決まったカリキュラムがないため、生徒一人ひとりに応じた対応も可能です。
また近年では、ICTを利用したオンラインでのフリースクールも登場し始めています。
不登校以外にも、ひきこもりやカウンセリング、医療機関と連携している施設もあるため、一度施設を見学に行くのも良いかもしれません。
未来地図|先輩ママたちが運営する不登校の道案内サイト
【2023年最新】全国のフリースクール情報一覧(全688件)
↑こちらから全国のフリースクールを検索できます。
学びの多様化学校(不登校特例校)
特例校として平成17年7月から実施された国による政策です。
当初は不登校特例校と言われていましたが、近年「学びの多様化学校」に名称が変更されました。
「不登校児童生徒に配慮した教育が必要だと認められた場合」に適応され、「特別の教育課程を編成して教育を実施できる」制度となっています。
通常の授業ではカリキュラムに則り一定のスピードで進みますが、学びの多様化学校(不登校特例校)では、必ずしもカリキュラム通りに進める必要がないため、不登校児童・生徒の能力に合わせた教育課程の実施が可能となります。
そのほか、少人数制の導入や習熟段階別の指導、児童・生徒の状況に応じた支援を行なっています。
文部科学省による設置一覧はコチラ↓
学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧(令和5年)
学びの多様化学校リーフレットはコチラ↓
文部科学省|誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策COCOLOプラン
ホームスクール
ホームスクールとは、文字通り家庭で教育を行うことをいいます。
欧米では珍しくないスタイルですが、日本でも徐々に知られるようになってきました。
しかし日本では中学までは義務教育であるため、不登校になってしまった生徒への、支援制度として行われているのが一般的です。
教育機会確保法まとめ
教育機会確保法について簡単に解説しました。一口に不登校といっても、その原因や現状は多岐に及びます。
教育機会確保法の施行により、お子さんだけでなく、保護者の方にとっても選択肢が広がりました。
何か少しでも不安を抱える保護者の方がおられましたら、各自治体やフリースクール等に相談してみてはいかがでしょうか。







最近のコメント