強度行動障害をわかりやすく解説!好発年齢や相談支援、アプローチ方法は?
この記事では、強度行動障害について包括的に解説します。
心理職等に携わる方ならご存じの方も多いかもしれませんが、初めて耳にしたという方が多いのではないでしょうか。
強度行動障害は、「障害」という名称から、ある種の病気であると捉えられがちです。
しかしじつは、先天的(生まれながら)のものではなく、生活環境などによって生じる、「二次的障害」と考えられています。
この障害は、本人が苦しいのはもちろん、周囲の人々にも大きなダメージが及びかねない障害です。
そこで本記事では、強度行動障害についてわかりやすく説明しながら、相談支援やアプローチについて解説します。
この記事が、少しでも障害を知るきっかけ、そして理解につながる機会となれば幸いです。
強度行動障害とは?その定義と特徴

強度行動障害は、医学的な診断名ではなく、行政・福祉分野で使用される用語です。
この状態は、個人の行動が著しく激しく、頻繁に発生することで、本人や周囲の生活に重大な影響を及ぼすケースが少なくありません。
具体的には、以下のような行動が高い頻度で見られます。
- 自傷行為:自分の体を激しく叩いたり、傷つけたりする
- 他害行為:他人を叩いたり、蹴ったりする
- 器物破損:家具やガラスなどを激しく壊す
- 異食行動:食べられないものを口に入れる
- 睡眠障害:睡眠サイクルが大きく乱れる
- 激しいこだわり:強い指示があっても自分のやり方を変えられない
これらの行動は、本人の健康を損なうだけでなく、周囲の人々の生活にも大きな影響を与えます。
そのため、特別な配慮と支援が不可欠です。
参考|厚生労働省|強度行動障害がある人
強度行動障害の発生メカニズム:環境との相互作用
冒頭で書いたように、強度行動障害は生まれつきの障害ではありません。
むしろ、何らかの障害をベースとして、環境との不適応によって生じる二次的な障害と考えられています。
例えば、自閉症スペクトラム障害(ASD)や知的障害のある方が、適切な支援や理解を得られない環境で生活を続けると、強度行動障害の状態に陥る可能性が高まります。
これは、障害特性と環境のミスマッチが、長期間にわたって蓄積された結果といえるでしょう。
参考|国立障害者リハビリテーションセンター|発達障害情報・支援センター|強度行動障害支援者研修資料
参考|東京都教育委員会ホームページ|1、強度行動障害とは何か
強度行動障害の発生年齢と性別差
強度行動障害の発生時期については、個人差が大きいものの、いくつかの傾向が観察されています。
厚生労働省の調査によると、多くのケースで思春期以降に症状が顕著化する傾向が見られます。
特に、中学校から高校にかけての時期に行動障害が激しくなるケースが多いようです。
一方で、学校卒業後に比較的落ち着くケースも報告されており、環境の変化が症状に影響を与える可能性を示唆しています。
性別については、大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課が2015年(平成27年)に実施した調査※によると、男性512名、女性167名と、およそ3対1の比率で男性に多い傾向が見られました。
また、2018年(平成30年)に島根県で行われた調査※でも、強度行動障害者の7割以上が男性であることが報告されています。
これらのデータは、強度行動障害の発生に性別が関与している可能性を示唆していますが、その理由については更なる研究が必要です。
※大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課|強度行動障がい児者実態調査 (障がい者)結果概要(平成27年3月)
※平成30年度強度行動障がい(児)者|実態調査報告書~島根県~
強度行動障害の支援:5つの重要な原則
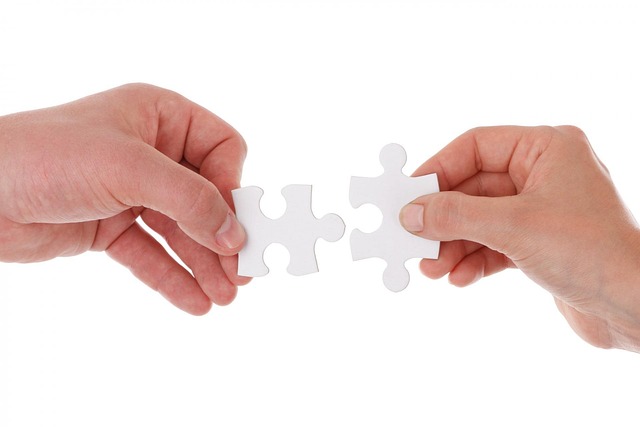
障害に対して、どのような支援が実施されているのでしょうか。
以下では、その支援体制について簡単に紹介します。
支援のあり方
厚生労働省は、強度行動障害のある人々を支援するための5つの重要な原則を提示しています。
これらの原則は、2024年(令和6年)現在も有効とされ、多くの支援現場で活用されています。
- 安心して通える日中活動の場の確保
- 居住空間の物理的構造化
- 一人で過ごせる活動時間の確保
- 明確で一貫したスケジュールの提供
- 安全な移動手段の確保
これらの原則は、強度行動障害のある方の生活の質を向上させ、問題行動を軽減するために重要な役割を果たします。
例えば、物理的構造化された環境は、視覚的な手がかりを提供し、不安や混乱を軽減することができます。
また、一貫したスケジュールは、予測可能性を高め、ストレスを軽減する効果が期待できるでしょう。
参考|厚生労働省|強度行動障害がある人p4
強度行動障害への対応:専門的な支援の重要性
強度行動障害への対応には、高度な専門知識と経験が必要であり、専門的な訓練を受けた支援者による介入が不可欠です。
2024年(令和6年)現在、日本全国で強度行動障害支援者養成研修が実施※されており、多くの福祉専門家がこの分野のスキルアップを図っています。
これらの研修では、行動分析学の知見を活用した支援技法や、環境調整の方法などが学ばれています。
また、医療との連携も重要です。
障害の背景には、身体的な不調や精神的なストレスが隠れていることもあるため、総合的なアプローチが不可欠であるのは言うまでもありません。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、さまざまな点で強度行動障害のある人に対する支援体制の拡充が図られています。児童発達支援や放課後等デイサービスで、強度行動障害のある子どもへの支援についても拡充が図られています。
※参考例|東京都福祉局|強度行動障害支援者養成研修
※参考例|藤仁館医療福祉カレッジ|埼玉県・群馬県知事指定・強度行動障害支援者養成研修
参考|厚生労働省|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
参考|厚生労働省|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
相談支援体制:地域で支える仕組み
この障害に悩む方やその家族を支援するため、全国各地に相談支援事業所が設置されています。
これらの事業所は、以下の3つに大別されます:
- 一般相談支援事業所
- 特定相談支援事業所
- 基幹相談支援センター
例えば、東京都では「とうきょう福祉ナビゲーション」※で、各地域の相談支援事業所を検索できます。
また、他の都道府県でも「〇〇県 相談支援事業所」とインターネットで検索することで、近くの支援機関を見つけられるはずです。
これらの相談支援事業所では、専門的な知識を持つ相談員が、個々のケースに応じた支援計画の作成や、関係機関との連絡調整などを行っています。
早期の相談と適切な支援につなげることで、予防や軽減に大きな効果が期待できるでしょう。
※福ナビ|とうきょう福祉ナビゲーション
強度行動障害の治療法:包括的アプローチの重要性
この障害に対する「治療」は、単一の方法ではなく、包括的なアプローチが必要です。
以下に、主な介入方法をいくつか紹介します。
- 行動療法: 応用行動分析(ABA)などの手法を用いて、問題行動の機能を分析し、適切な行動を強化。
- 環境調整: 感覚過敏などの特性に配慮した環境づくりを行い、ストレス要因を軽減。
- コミュニケーション支援: 絵カードや補助的なデバイスを使用して、本人の意思表示を助けます。
- 薬物療法: 必要に応じて、精神科医の指導のもと、症状を和らげるための薬物の使用。
- 感覚統合療法: 感覚処理の問題に対応し、適切な感覚入力を提供。
- 家族支援: 家族に対するカウンセリングや教育的支援も、間接的に本人の状態改善につながります。
これらの方法を組み合わせ、個々の状況に応じた支援計画を立てることが重要です。
また、定期的な評価と計画の見直しを行い、常に最適な支援を提供し続けることが求められます。
2024年(令和6年)現在、バーチャルリアリティ(VR)を用いたソーシャルスキルトレーニング※など、新しい技術を取り入れた支援方法も研究されており、今後の発展が期待されています。
※大塚製薬株式会社|ソーシャルスキルトレーニング(SST)支援VRプログラム
今回のまとめ
強度行動障害は複雑で挑戦的な課題ですが、適切な理解と支援があれば、多くの方々の生活の質を大きく向上させることができます。
社会全体で理解を深め、支援の輪を広げていくことが、今後ますます重要になってくるでしょう。
より詳しい治療法や判定シートを提供してくれているウェブサイトもありますので、関心のある方は以下のリンクを参照ください。
治療法について
・和歌山県強度行動障害支援者養成研修(実践研修)|強度行動障害と医療
・国立障害者リハビリテーションセンター|強度行動障害医療的立場から
強度行動障害判定シート
厚生労働省|強度行動障害児(者)の医療度判定基準






最近のコメント