児童相談所と子ども家庭支援センター:役割の違いと子育て支援の実際、相談窓口をわかりやすく解説!
この記事では、児童相談所と子ども家庭支援センターについて簡単に紹介します。
子育て中の親御さんにとって、育児の悩みは尽きないもの。
相談できる相手が身近にいれば心の支えとなりますが、
・「誰にも相談できない」
・「どこに相談したら良いかわからない」
という方も意外に多いのが現状です。
誰にも相談できない状況が続くと、ご自身だけでなく、お子さんにも悪影響が及ぶ可能性も考えられます。
しかし、そんな時に支えとなるのが、「児童相談所」や「子ども家庭支援センター」といった支援施設です。
今回は両施設のポイントをわかりやすく解説していますので、子育て中の親御さんの一助になれば幸いです。
児童相談所・子ども家庭支援センターとは

読者の方の中には、児童相談所と子ども家庭支援センターの違いについて、ご存じない方も多いと思います。
そこで以下では、両施設の違いについて、役割を踏まえつつ解説します。
児童相談所:子どもの権利を守る最前線
児童相談所(児相)は、子どもの権利擁護の最後の砦として重要な役割を果たしています。
その大きな役割は、18歳未満の子どもに関する問題への支援です。
何よりも子どもの利益を最善とし、一人ひとりの子どもに適した支援や指導を行うことを目的としています。
1947年の児童福祉法制定以来、社会の変化とともにその機能を拡充しており、各都道府県に設置されています。
児童福祉法では、2016(平成28)年の改正によって特別区でも設置できるようになりました。2025(令和7)年1月時点で、東京都の複数の区で設置が進んでいます。
なお、いずれの施設においても料金は無料です。
児童相談所主な役割
・相談機能:児童福祉司や児童心理司が中心となり、虐待、非行、発達障害など、子どもに関するあらゆる相談に対応します。2022年度の児童虐待相談対応件数は21万件を超え、年々増加傾向にあります。
・一時保護機能:緊急性の高いケースでは、子どもを一時的に保護します。2022年度の一時保護件数は約3万件で、虐待や非行などが主な理由です。
・措置機能:家庭での養育が困難な場合、児童養護施設への入所や里親委託などの措置を行います。2022年度末時点で、約4万5千人の子どもが社会的養護のもとで生活しています。
・専門的判定:医学、心理学、教育学などの専門家チームが子どもの状況を多角的に判断します。
・市町村支援:複雑なケースや専門的な判断が必要な場合に、市町村の相談窓口をバックアップします。
児童相談所における支援者
なお、児童相談所では次の資格を持つ専門家から支援が受けられます。
状況に応じて、幅広い対応が可能です。
・児童福祉司(ケースワーカー)
・児童心理司
・医師(小児科や精神科医)
など。
ケースによっては、複雑な問題を抱えるお子さんもいます。
そのため、複合的な支援を受けられるのも大きなメリットと言えるでしょう。
児童相談所の取り組み事例
近年のIT技術の進歩に伴い、児童相談所でもITを活用した取り組みが積極的に採用され始めています。
例えば東京都。
東京都では、2019年(令和元年)から児童相談所の機能強化を図り、2024年(令和6年)までに4か所の増設を予定しています。
また、AIを活用した虐待リスク分析システムの導入も進めており、早期発見・早期対応の体制づくりが強化されつつあるようです。
子ども家庭支援センター:地域に根ざした子育て支援の拠点
子ども家庭支援センターは、2022年のこども家庭庁設置法の成立を機に、その役割がより明確化されました。
児童相談所は都道府県の広域エリアごとの設置なのに対して、子ども家庭支援センターは区市町村単位での設置です。
地域に密着した子育て支援の中核機関として、予防的アプローチから具体的支援まで幅広く対応することが大きな役割です。
また、地域によっては、「児童家庭支援センター」の名称で呼ばれることもあり、通称「子家(コカ)/児家(ジカ)」または「子家セン/児家セン」とも言われます。
子ども家庭支援センターの具体的な機能
具体的な支援として、主に以下のものが挙げられます。
・ワンストップ相談窓口:妊娠期から18歳までの子育てに関するあらゆる相談に対応。
2023年度の相談件数は、全国で約100万件に上ると推計されています。
・利用者支援事業:子育て家庭のニーズに合わせて、適切なサービスや施設を紹介。
・地域子育て支援拠点事業:「あそびのひろば」などを通じて、親子の交流や情報交換の場を提供。
2023年度は全国で約7,500か所が運営されています。
・養育支援訪問事業:特に支援が必要な家庭に対して、保健師や助産師が訪問し、具体的な育児指導を行う。
・子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ):保護者の疾病や仕事等の理由で、一時的に子どもを預かるサービスを提供。
子ども家庭支援センターの先進的取り組み事例
子ども家庭支援センターの取り組みは、各自治体ごとに異なります。
例えば横浜市では、2023年(令和5年)から全18区に「こども家庭総合支援拠点」を設置。
各区の子ども家庭支援センターと連携して、より細やかな支援体制が取れるよう整えられつつあります。
また、コロナ禍においては、オンライン相談システムの導入し、途切れのない支援実現を目指しています。
児童相談所と子ども家庭支援センターの連携:シームレスな支援体制の構築
児童相談所と子ども家庭支援センターの連携は、子どもと家庭を切れ目なく支援する上で不可欠と言えるでしょう。
では、両施設の連携例として具体例を見てみましょう。
・要保護児童対策地域協議会:両機関を含む多機関が定期的に会議を開き、支援が必要な子どもや家庭の情報を共有し、支援方針を決定します。2023年度(令和5年度)は全国の99.9%の市区町村で設置されています。
・ケース移管:子ども家庭支援センターで対応していたケースが深刻化した場合、児童相談所に引き継ぎます。逆に、児童相談所の関与が終了したケースを地域で見守る際は、子ども家庭支援センターが中心となって支援を継続します。
・共同訪問:虐待が疑われるケースなどでは、両機関の職員が一緒に家庭訪問を行い、多角的な視点で状況を把握します。
・研修の共同実施:両機関の職員が合同で研修を受けることで、知識や技術の向上と相互理解を深めています。
また、連携強化の取り組みも進められています。
例えば大阪府では、2022年(令和4年)から児童相談所と子ども家庭総合支援拠点(子ども家庭支援センターの機能を含む)の一体的運営を開始。
より迅速で効果的な支援体制を構築しています。
児童相談所と子ども家庭支援センター:利用者の視点から見た支援サービス
両機関が提供するサービスは、子育て家庭のニーズに応じて多岐にわたります。
サービスの詳細と利用状況:
- 電話相談:児童相談所虐待対応ダイヤル「189」は、2023年度の利用件数が約30万件に達し、前年比20%増となりました。
- ショートステイ:東京都の利用実績では、2022年度に約5,000件の利用があり、特に0〜3歳児の利用が多くなっています。
- 育児支援ヘルパー派遣:横浜市の2023年度利用実績では、約2,000世帯が利用し、産後うつの予防にも効果を上げているようです。
- ファミリー・サポート・センター:全国で約95万件(2022年度)の利用があり、働く親の強い味方となっています。
利用者の声
実際の利用者の声を紹介します。
両施設を利用することで、ポジティブな変化が訪れることが多いようです。
また、自分と同じような状況にある利用者と「横のつながり」ができるケースもあります。
横のつながりができれば、お互いの状況を話し合えるため、気持ちが軽くなることもあるでしょう。
・「児童相談所の一時保護で我が子と離れる時は辛かったけど、その間に自分自身のケアもでき、家族関係を立て直すきっかけになりました。」(40代母親)
・「子ども家庭支援センターの広場で知り合った母親たちとの交流が、育児の孤立感を解消してくれました。」(30代母親)
相談を検討すべき具体的な状況

- 子どもの発達:言葉の遅れ、コミュニケーションの難しさ、落ち着きのなさなどが気になる場合
- 育児ストレス:子どもへの否定的な感情が強くなる、イライラが収まらないと感じる場合
- 家族関係:夫婦間の不和、祖父母との育児方針の違いで悩んでいる場合
- 虐待の可能性:感情的に子どもを叩いてしまう、食事を与えるのを忘れてしまうなどの経験がある場合
もちろん、これらの状況はあくまで一例です。
上記以外のことでも、気になることがあれば遠慮せずに相談してみてください。
相談方法の選択肢
また、相談方法も複数用意されています。
置かれた状況に合わせて、利用しやすい相談方法を選びましょう。
- 電話相談:匿名で気軽に相談できる「189」や「24時間子供SOSダイヤル」
- オンライン相談:コロナ禍を機に多くの自治体で導入が進んでいます
- 対面相談:子ども家庭支援センターや保健センターでの面談
- SNS相談:LINEなどを活用した相談窓口も増えています
早期相談の効果
厚生労働省の調査によると、虐待による重大事故の約7割は、事前に何らかの兆候があるとのこと。
早期の相談や支援介入により、深刻な事態を防ぐことができる可能性が高まります。
そのため、何らかの変化を感じた場合は、躊躇せず積極的に相談窓口を利用してください。
児童相談所と子ども家庭支援センターまとめ
児童相談所と子ども家庭支援センターは、それぞれの特性を活かしながら、子育て家庭を多角的にサポートしています。
両機関の存在と役割を知り、適切に活用することで、子育ての喜びをより深く感じることができるでしょう。
社会全体で子育てを支える意識が高まる中、これらの機関の重要性は増しています。
子育ては決して一人で抱え込むものではありません。
困ったときは、ぜひこれらの支援機関を頼りにしてください。
あなたの勇気ある一歩が、きっと子どもたちの明るい未来につながるはずです。
最新記事一覧
- 多子世帯の大学無償化とは?簡単に解説!条件や申請方法、成績は関係ある?
- チャレンジスクールの志願申告書はどう書く?高校一覧や学費、倍率も徹底解説します!
- 少年鑑別所の入所数は増えている?少年院との違いや期間、相談窓口を簡単に解説!
- 要対協に守秘義務はある?メンバー構成や担当者の資格を解説!
- 認定こども園とは?わかりやすく解説!保育園との違いやデメリット、対象年齢は?
児童相談所と子ども家庭支援センター:参照サイト・リンク集
なお、この記事は以下の情報をもとに作成しています。
より詳しい情報や地域の施設について知りたい場合は、以下のリンクをご参照ください(外部リンクに飛びます)
・こども家庭庁|児童相談所一覧
・文部科学省|「24時間子供SOSダイヤル」について
・厚生労働省|こども家庭センターについて
・東京都|子ども家庭支援センター
・こども家庭庁|こども家庭センターガイドラインのポイント
・厚生労働省|児童相談所運営指針
👉児童相談所についての詳細は上記のサイトでご確認ください。
なお、令和6年3月30日、新たに児童相談所運営指針の全部改正についてが通知され、4月1日から改正された指針での運用が開始されました。
・東京都練馬区|子どもトワイライトステイ(夜間一時保育)





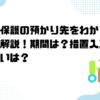

最近のコメント