児童福祉法とは?その理念や目的、改正のポイントは?児童福祉施設も併せて解説します!
この記事では、児童福祉法について紹介します。
「福祉六法」の1つである児童福祉法は、子どもたちの幸せと健やかな成長を守るための重要な法律です。
とはいえ、突然法律の話をされても戸惑ってしまう方も多いと思います。
そこで今回は、児童福祉法について大まかに説明しつつ、関連する児童福祉施設も併せて見てみましょう。
関連記事👉こども基本法
児童福祉法の基本理念と目的:子どもの幸せを第一に

児童福祉法※は、1947年(昭和22年)に制定された法律で、18歳未満のすべての子どもの福祉と権利を保障することを目的としています。
これまで幾度も改正がなされてきており、近年では、2022年(令和4年)6月8日に「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立。その後、2024年(令和6年)4月1日から新たに施行されています。
この法律の根幹にある理念は、「すべての児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない」というものです。
また、この法律では子どもの福祉を保障する責任を、保護者だけでなく国民全体、そして国と地方自治体にも課している点も特徴と言えるでしょう。
参考までに、児童福祉法の第一条及び第二条の原文を紹介します。
第一条:全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する
引用/児童福祉法 第一条
第二条:全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
引用/児童福祉法 第二条
このように、児童福祉法は「子どもの権利条約」の精神に基づいており、子どもたちが健康で幸せに成長できる環境を整えることも大きな目的です。
その他、児童福祉施設や児童福祉司、保育士の資格についての要件を定めているのも、児童福祉法によります。
※e-GOV法令検索|児童福祉法
参考|厚生労働省|児童福祉法の目的・理念(その1)
参考|こども家庭庁|令和4年6月に成立した改正児童福祉法について
児童福祉法の対象範囲:幅広い支援と保護の仕組み
児童福祉法が対象とする範囲は非常に広く、以下のような分野をカバーしています(例)。
- 児童相談所の設置と運営
- 保育所や児童養護施設などの児童福祉施設の基準
- 児童福祉司、児童委員、保育士の責務と資格要件
- 障がい児支援サービス
- 里親制度と養子縁組
- 児童虐待防止対策
など。
特に注目すべき点として、児童福祉法は母子保護も含んでいることが挙げられます。
例えば、第38条※では母子生活支援施設について規定しており、DV被害者などの保護を行う施設としての役割も担っています。
また、児童福祉法は「福祉六法」の一つです。
福祉六法とは、社会福祉の基本となる6つの法律のことで、
児童福祉法の他に、
・生活保護法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法
・老人福祉法
・母子及び父子並びに寡婦福祉法
が含まれます。
※e-GOV法令検索|児童福祉法
参考|厚生労働省|福祉事務所
児童福祉法の最新改正:2024年4月施行の主要ポイント

児童福祉法は時代の変化に合わせて繰り返し改正されてきました。
最新の大きな改正は、上述した2022年(令和4年)6月8日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」※で、2024年(令和6年)4月1日から施行されました。
この改正では、子どもや家庭の養育環境への支援が強化され、子どもの権利を保護する福祉施策のさらなる推進が期待されています。
主な改正ポイントは以下の4項目です。
1. こども家庭センターの設置
改正の目玉の一つが、「こども家庭センター」※の設置です。
これは、すべての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な支援を行う施設で、市区町村が設置します。
またこのセンターは、相談業務のほか、支援が必要な子どもや妊産婦への支援計画(サポートプラン)作成も担当します。
これに伴い、既存の子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターは見直され、こども家庭センターに集約される見込みです。
また、子ども家庭福祉の現場で十分な専門性を持った人材を輩出するため、2024年から認定資格「こども家庭ソーシャルワーカー」※の運用が始まります。
※こども家庭庁|こども家庭センターガイドラインのポイント
※日本福祉大学|こども家庭ソーシャルワーカーとは? 資格の内容や取得方法等を解説【専門家監修】
2. 虐待防止と児童相談所の体制強化
児童虐待の増加を受け、虐待防止と児童相談所の体制強化も改正の重要なポイント。
具体的には以下の変更が行われます。
- 都道府県の業務として「子どもの権利擁護の環境整備」を明確化
- 児童相談所が行う措置の各段階で、子どもの意見聴取を実施
- 一時保護の際、裁判官による司法審査の導入
特に注目すべきは、一時保護に関する改正です。
これまで児童相談所の判断のみで行われていた一時保護に、裁判官の審査が加わることで、子どもの権利と安全のバランスを取る試みが行われます。
緊急性が高い場合は事後審査となりますが、原則として事前に裁判官が発行する一時保護状に基づいて実施されることになりました。
3. 日本版DBS導入への取り組み
近年、ベビーシッターによる犯罪事件などを受け、教育・保育に携わる職業に就く際に性犯罪歴がないことを証明する「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」制度の導入が議論されています。
児童福祉法では、これに関連して保育士の登録取り消し事由や欠格期間について改正が行われました。
参考|朝日GLOBE +|子どもを性犯罪から守る「日本版DBS」とはどんな制度?概要や課題を分かりやすく解説
関連|こども家庭庁|こども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進
4. 障害児支援の充実
児童福祉法における障害児支援も重要な項目です。
改正では、障害のある子どもに対する支援事業がさらに充実し、年齢や障害の程度に応じたきめ細かいサービスが受けられるようになります。
主な支援サービスには以下のようなものがあります。
- 児童発達支援:主に未就学児を対象とした療育支援
- 放課後等デイサービス:就学児を対象とした放課後や長期休暇中の支援
- 医療型児童発達支援:医療的ケアが必要な児童への支援
- 保育所等訪問支援:保育所や学校等を訪問しての支援
これらのサービスを通じて、障害のある子どもたちの成長と自立を支援し、
社会参加を促進することを目指しています。
※厚生労働省|児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第6 6号)の概要
児童福祉施設の種類と役割:子どもたちを支える多様な施設
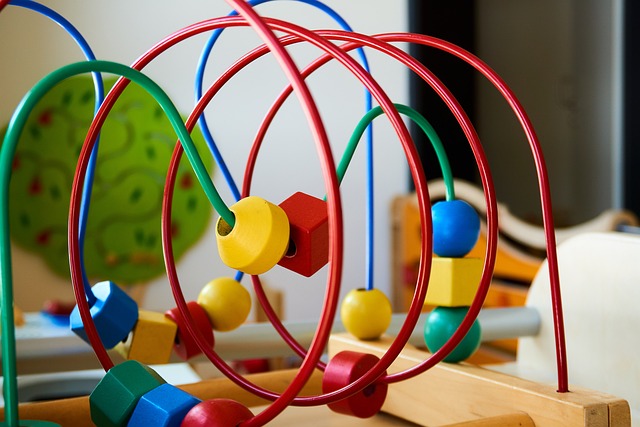
児童福祉法では、さまざまな状況にある子どもたちを支援するために、多様な児童福祉施設が規定されています。全体で12の施設が設置されていますが、ここでは、6つの児童福祉施設の種類とその役割について見てみましょう。
1. 乳児院
主に0歳から2歳くらいまでの乳幼児を対象とした施設です。
- 保護者が病気や経済的理由で養育できない場合
- 虐待や養育放棄(ネグレクト)から子どもを保護する必要がある場合
- 養子縁組が成立するまでの一時的な保護
乳児院では、24時間体制で専門的な養育が行われ、子どもの健康と発達を支援します。
また、家庭復帰や里親委託に向けた取り組みも行われています。
2. 児童養護施設
児童養護施設は、主に2歳から18歳までの子どもを対象とした入所施設です。
家庭での養育が困難な子どもたちが生活しています。
- 保護者の死亡、行方不明、離婚などによる養育困難
- 虐待やネグレクトからの保護
- 経済的理由による養育困難
施設では、衣食住の提供だけでなく、学習支援、進路指導、心理的ケアなど、
子どもたちの成長と自立に向けた総合的な支援が行われています。
さらに近年は、大舎制から小規模グループケアへの移行が進められ、
より家庭的な環境での養育が目指されるようになりました。
3. 児童自立支援施設
児童自立支援施設は、主に不良行為をした子どもや、
家庭環境などの理由で生活指導等を要する子どもたちを対象としています。
対象年齢は概ね小学校高学年から18歳未満です。
- 小規模な寮舎での生活指導
- 学習支援と作業指導
- 心理治療や家族療法の実施
目標は、子どもたちの自立を支援し、健全な社会性を育むことです。
また、退所後の支援にも力を入れており、社会復帰のサポートを行っています。
関連記事👉被害者支援
4. 母子生活支援施設
母子生活支援施設は、18歳未満の子どもとその母親が一緒に入所できる施設です。
主に以下のような場合に利用されます。
- DV(ドメスティックバイオレンス)からの避難
- 経済的理由による住居喪失
- ひとり親家庭の自立支援
施設では、安全な生活環境の提供、子育て支援、就労支援など、
母子の自立に向けた総合的なサポートが目的です。
5. 児童発達支援センター
児童発達支援センターは、障害のある児童やその家族を対象とした通所施設です。
- 日常生活における基本的な動作の指導
- 知識技能の付与
- 集団生活への適応訓練
センターでは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門家が連携して、
子どもの発達を総合的に支援します。
また、地域の障害児支援の中核的な役割も担っています。
6. 児童心理治療施設
児童心理治療施設は、心理的問題を抱える児童を対象とした入所施設です。
- 不登校や引きこもりの子ども
- 虐待などのトラウマを抱える子ども
- 発達障害や愛着障害のある子ども
施設では、心理療法や生活療法、学習支援などを通じて、子どもたちの心の回復と健全な発達を支援します。
家族療法も重視されており、家族関係の改善にも取り組んでいます。
これらの児童福祉施設は、どれも社会のセーフティネットとして重要な役割を果たしています。
しかし同時に、すべての子どもが家庭的な環境で育つことができる社会を目指す努力も重要です。
参考|厚生労働省|社会的養護の施設等について
参考|浜松静岡介護求人センター|【2024年最新】児童福祉施設について徹底解説!
児童福祉法の運用と今後の課題とまとめ
児童福祉法は、子どもたちの幸せと健やかな成長を守るための重要な法的基盤です。
しかし、法律があるだけでは十分ではありません。
その理念を実現するためには、社会全体で子どもの権利を尊重し、
支援の体制を整えていく必要があります。
さらに、今後の課題としては、以下の点が挙げられます。
- 児童相談所の人員不足と専門性の向上
- 虐待の早期発見と適切な対応
- 里親制度の普及と支援の充実
- 障害児支援サービスの地域格差の解消
- 子どもの貧困対策の強化
こうした課題に取り組むためには、国や地方自治体の努力だけでなく、私たち一人ひとりが児童福祉法の理念を知り、子どもたちの幸せのために行動することが重要です。
さらに、児童福祉法は、時代とともに変化する子どもたちを取り巻く環境に対応し、常に進化し続けています。
この記事が、子どもの権利と福祉について改めて考え、みなさんが行動する機会の一助となれば幸いです。
最新記事一覧
- チャレンジスクールの志願申告書はどう書く?高校一覧や学費、倍率も徹底解説します!
- 少年鑑別所の入所数は増えている?少年院との違いや期間、相談窓口を簡単に解説!
- 要対協に守秘義務はある?メンバー構成や担当者の資格を解説!
- 認定こども園とは?わかりやすく解説!保育園との違いやデメリット、対象年齢は?
- 懲戒権の削除について簡単に解説!見直しの理由やしつけのあり方を考える






最近のコメント