インクルーシブ教育システムをわかりやすく解説!理念や目的、メリットや今後の課題は?
この記事では、昨今注目を集めているインクルーシブ教育システムをわかりやすく解説します。
このシステムは、障害の有無に関係なくすべての子どもたちが共に学び、成長できる教育環境を目指すものです。
2008年に発効された国連の「障害者の権利に関する条約」を契機に、現在では世界中で導入が進められています。
では、具体的にどのような取り組みなのでしょうか?インクルーシブ教育システムについてご存じない方でも、きっとご理解いただけると思いますよ!
インクルーシブ教育システムの基本理念と歴史的背景

インクルーシブ教育システムは、英語で「inclusive education system」と表記され、「包括する教育制度」と訳されることもあります。
その主な理念は、生徒の多様性を最大限尊重しつつ、障害がある・なしに関わらず、精神的・身体的な能力を可能な限り発揮し、同じ場所で共に学ことを目的としています。
2006年(平成18年)に国連で初めて提唱され、以降「特別支援教育」という枠組みを超えて、教育のあり方そのものを見直すきっかけとなりました。
日本は2007(平成19年)年9月に同条約に署名し、2014年(平成26年)1月に批准しています。
2022年(令和4年)の段階で、世界185カ国が締結しており、グローバルスタンダードとしての地位を確立しつつあります。
インクルーシブ教育システムの具体的な定義について示されている、「障害者の権利に関する条約第24条」(一部抜粋)を見てみましょう。
- (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
- (b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
- (c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
引用|文部科学省|障害者の権利に関する条約について第24条
また、このシステムの核となる考え方として以下の3つが挙げられます。
1、人間の多様性の尊重
2、障害者の能力開発の最大化
3、自由な社会への効果的な参加の促進
参考|文部科学省|共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告) 概要
参考|独立行政法人|国立特別支援教育総合研究所|「インクルーシブ教育システム」とは?
日本における実践と「合理的配慮」の意味
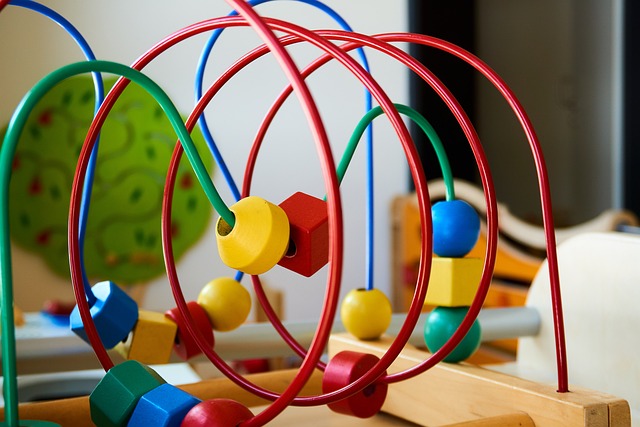
インクルーシブ教育システムの実現を目指す上で、日本の教育現場では「合理的配慮」という概念を重要視しています。
合理的配慮とは、個々の特性や状況に応じて生じる困難さを解消するための、個別の調整や変更のことです。
これは、教育を受ける権利を実質的に保障するための重要な取り組みであり、例えば具体例として、
- 教材のデジタル化や音声化
- 座席位置の工夫
- 試験時間の延長
- 補助具の使用許可
- コミュニケーション方法の調整
などの実施が挙げられます。
また、学びの場として、たとえば次のような選択肢が用意されています。
- 通常の学級での学習
- 支援員による個別サポート
- 教材や指導方法の工夫
- 学級全体での相互理解の促進
- 通級による指導
- 特別な指導を必要な時間だけ受ける
- 在籍学級での学習を基本としつつ専門的支援を受ける
- 個々の課題に応じた効果的な指導
- 特別支援学級での学習
- 少人数でのきめ細かな指導
- 個々の特性に応じた教育課程
- 特別支援学校での専門的な教育
- 専門性の高い教職員による指導
- 充実した施設設備の活用
このように、インクルーシブ教育システムでは、合理的配慮を考慮に入れつつ、多角的な視点で教育を提供することが求められます。
参考|文部科学省|共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告) 概要|3、障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備
インクルーシブ教育がもたらす効果

インクルーシブ教育システムの導入は障害のある・なしに関わらず、多くのポジティブな効果をもたらすことが予想されています。
それぞれの効果について見てみましょう。
障害のある児童生徒への効果
- 社会性の向上と孤立の防止
- 多様な人々との交流機会の増加
- 実践的なコミュニケーション能力の育成
- 社会参加への自信構築
- 自己肯定感の育成
- 個性や能力の認識と活用
- 周囲からの理解と承認の実感
- 多様な学習機会の確保
- 幅広い知識や経験の獲得
- 興味関心に応じた学習の深化
障害のない児童生徒への効果
- 多様性への理解促進
- 違いを認め合う心の育成
- 偏見や固定観念からの解放
- 多様な価値観への開かれた姿勢
- 共感力の向上
- 他者への思いやりの醸成
- 相互扶助の精神の育成
- 社会的責任感の形成
- 共生社会の担い手としての成長
- インクルージョンの実践的理解
- 未来社会への積極的な関与
特に注目すべきは、この教育システムが「共生社会」の実現に向けた重要な基盤となっている点です。
子どもたちが早い段階から多様性を受け入れることで、将来的な社会全体のインクルージョンが促進されることが期待されます。
インクルーシブ教育システムの課題と今後の展望
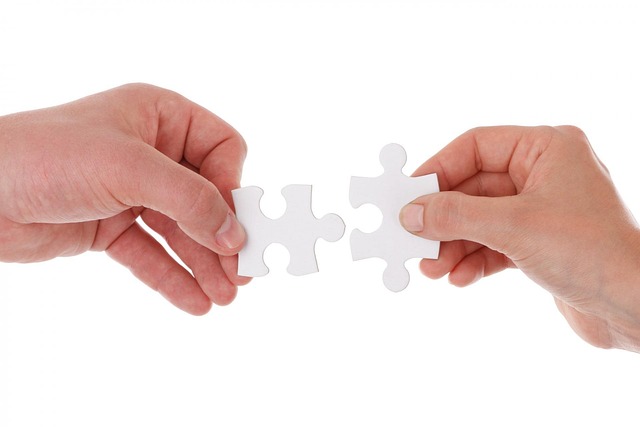
ここまで、インクルーシブ教育システムの理念やポジティブな側面を紹介しました。
とはいえ、実現までにはかなりの課題を解決しなくてはならないのが現状です。
そこで、現在考えられている課題について、いくつか紹介します。
1. 環境整備の遅れ
大きな課題として挙げられのが、環境整備の遅れです。
令和4年9月時点での公立小中学校のバリアフリー化の状況※は以下の通り。
- バリアフリートイレの設置率:70.4%
- スロープ等による段差解消:61.1%
- エレベーター設置率:29.0%
確かに、以前と比べるとバリアフリー化が進んではいるものの、しかしそれでもなお、インクルーシブ教育システムを実現するためには十分とは言えません。
※文部科学省|学校施設のバリアフリー化の推進
2. 教員の専門性向上の必要性
また、インクルーシブ教育システムを構築するにあたっては、教員側の正確な理解が不可欠となります。
- 特別支援教育に関する知識・技能の習得
- 発達障害児への理解と支援スキル
- 管理職を含めた学校全体の専門性向上
3. 人材・リソースの不足
教育を提供する側の人手不足も大きな課題です。
ICT技術の進歩により、児童・生徒への行き届いた配慮が広がる一方、その分、教職員への負担が増大しています。
さらにそこに、インクルーシブ教育システムについての知識・配慮が必要となると、現在の体制ではとても対処しきれません。
そのため、教職員の人材確保や、専門家(支援員)の増員は避けられません。
具体的には、以下のことで挙げられます。
- 教員の絶対数の不足
- 支援員等の外部人材の確保
- 効果的な支援体制の構築
また、こうした課題の他にも、周囲の児童・生徒への影響や周囲の理解、さらには、合理的配慮についての理解といった課題も挙げらます。
教員の専門性向上については、研修制度の充実や外部専門家との連携強化が検討中ではあるものの、日本においては課題が山積しているのが現状です。
参考|文部科学省|共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)
参考|国立特別支援教育総合研究所|日本における インクルーシブ教育システム構築 の取組と課題
これからのインクルーシブ教育システムに向けて

こうした山積する課題を踏まえた上で、インクルーシブ教育システムの更なる発展のために、今後どのような試みが必要なのでしょうか。
今後の展望について5つの観点から見てみましょう。
段階的かつ計画的な環境整備の推進
- 予算の効率的な活用
- 優先順位を考慮した整備計画の立案
- 地域特性に応じた施設改修
教員研修の充実と専門性の向上
- オンライン研修の活用
- 実践的なワークショップの実施
- 専門家による継続的なサポート
地域社会との連携強化
- 地域人材の活用
- 企業との協働
- NPO・ボランティア団体との協力
保護者への理解促進と支援体制の構築
- 定期的な情報共有
- 相談窓口の充実
- 保護者間のネットワーク形成
定期的な効果測定と改善策の実施
- 客観的な評価指標の開発
- データに基づく改善策の立案
- 成功事例の共有と活用
イタリアのように特別支援学校を完全に廃止した国もある中で、日本は独自のアプローチで着実に前進を続けています。
各国の状況を見ながら、日本の教育環境や文化に適した形で、インクルーシブ教育を発展させていくことが求められています。
参考|文部科学省|インクルーシブ教育システム構築事業
インクルーシブ教育システム:まとめ
今回はインクルーシブ教育システムについて、その理念や課題、展望を解説しました。
本システムについて「初めて聞いた」という方も多いのではないでしょうか。
インクルーシブ教育の完成までには、多くの課題が残されています。
しかし、着実に課題をクリアすることで、子どもたちの可能性を広げ、誰もがお互いに理解し合える社会の実現へ近づきます。
そのためには、教育現場はもちろんのこと、地域や周囲の人々の理解も不可欠です。
社会全体にこのシステムが行き渡った時こそが、このプロジェクトの真の完成なのかもしれません。
文部科学省によるリーフレットはこちら👇
「だれでもいつでも学べる社会へ ー障害のある・なしに関係なく共に学べる生涯学習について」
関連記事👉就学相談で気を付けることとは?、特別支援学級



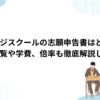



最近のコメント