保育所等訪問支援をわかりやすく解説!支援までの流れは?保護者の負担や申請も必要?
この記事では、保育所等訪問支援について解説しています。
「うちの子、集団行動が苦手みたい…」
「保育園や学校で、お友達と上手く関われているか心配…」
お子さんが保育所や幼稚園、学校といった集団生活の場で、何かしらの「しんどさ」を抱えているように見えるとき、保護者として何ができるだろうかと悩んでしまうことはありませんか。
そんな悩みに寄り添い、お子さんが安心して楽しく集団生活を送れるようサポートしてくれるのが保育所等訪問支援という公的サービスです。
専門知識を持つ支援員が、お子さんの通う保育所や学校などを定期的に訪問し、お子さん本人だけでなく、関わる先生方にも専門的なアドバイスをしてくれます。
「保育所等」という名称ですが、保護者の方が申請することで、小学生〜高校生まで利用できるのも特徴です。
この記事では、そんな心強い味方である「保育所等訪問支援」について、
- どんなサービスなの?
- 誰が利用できるの?
- 具体的に何をしてくれるの?
- どうすれば利用できるの?(流れや申請方法)
- 費用はどれくらいかかるの?
といった保護者の方が気になるポイントを、一つひとつ分かりやすく解説していきます。
関連記事👉放課後等デイサービス
保育所等訪問支援とは?専門家が学校や園を訪問する心強いサポート
出典:YouTube
まずは、保育所等訪問支援について簡単にまとめます。
障害のあるお子さんや、発達に特性のあるお子さんが、普段通っている保育所、幼稚園、小学校などの集団生活の場で、専門的な支援を受けられるようにする、児童福祉法に基づいた公的な福祉サービスです。
この制度の一番の目的は、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが地域社会の一員として共に育ち合う「インクルージョン」の考え方を実現することにあります。
「特別な場所」ではなく、お子さんが「いつもいる場所」に専門家が出向いてくれるのが大きな特徴です。
また、児童発達支援や放課後等デイサービスに併設されていることもあります。
そのため、すでにこれらをご利用の方は、あわせて相談してみるのもよいでしょう。
参考|子ども家庭庁|保育所等訪問支援ガイドライン(令和6年7月)
関連記事👉インクルーシブ教育システムとは?
どんな人が、どこに来てくれるの?
- 誰が?:保育士や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師など、子どもの発達支援に関する専門的な知識や経験を持つ「訪問支援員」が担当します。
- どこへ?:お子さんが通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高校、特別支援学校、さらには放課後児童クラブ(学童保育)やフリースクールなど、子どもが集団生活を営む様々な施設が対象です。
訪問支援員は、お子さんの様子を専門的な視点で観察し、一人ひとりの特性に合わせたサポートを行います。
具体的には、お子さん本人に直接関わる「直接支援」と、担任の先生など周囲の大人に助言をする「間接支援」を組み合わせて、お子さんが集団生活にスムーズに適応できるようお手伝いをしてくれます。
近年、この制度の認知度が高まるにつれて利用者数も増加し、厚生労働省の調査では、2021年から2022年の1年間で利用者数が約1.65倍に増加していることが報告されました※。
※参考|厚生労働省|障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況(令和4年度)
どんな子ども・施設が対象?診断書は必要?
「うちの子も対象になるのかな?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
保育所等訪問支援は、幅広いお子さんと施設を対象としています。
対象となる子ども
対象となるのは、0歳から18歳の誕生日を迎えるまでの、集団生活での困難さを抱えているお子さんです。
「障害のある子ども」が対象と聞くと、発達障害や知的障害、身体障害などの診断名が必要だと思われるかもしれませんが、医師の診断書や障害者手帳の有無は問われません。
例えば、
- 落ち着きがなく、じっとしていられない
- 集団での指示が通りにくい、みんなと同じ行動が苦手
- お友達とのトラブルが多い、コミュニケーションが上手くとれない
- こだわりが強く、かんしゃくを起こしやすい
- 特定のこと(音、光、触感など)にとても敏感
など、集団生活の中で何らかの困りごとを抱えているお子さんであれば、幅広く対象となり得ます。
知的障害を伴わない発達障害(グレーゾーン)のお子さんももちろん対象です。
「診断はないけれど、気になることがある」という段階で相談できるので、保護者の方にとって、安心できる制度となっています。
対象となる施設
訪問先も充実しています※。
- 保育所(認可・認可外問わず)、幼稚園、認定こども園
- 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
- 乳児院、児童養護施設
- 放課後児童クラブ(学童保育)
- その他、自治体が「児童が集団生活を営む施設」と認めるフリースクールなど
お子さんが日中の多くの時間を過ごす生活の場で、専門的な視点からのサポートを受けられるのが、この制度の大きな魅力です。
※参考|子ども家庭庁|保育所等訪問支援ガイドライン(令和6年7月)(詳細版①)
具体的にどんな支援をしてくれるの?「直接支援」と「間接支援」

では、訪問支援員は具体的にどのようなことをしてくれるのでしょうか。
支援内容は、上述のとおり、お子さん本人に直接働きかける「直接支援」と、お子さんを取り巻く環境に働きかける「間接支援」の2つに大きく分けられます。
それぞれ見てみましょう。
直接支援:子ども本人へのサポート
訪問支援員が、集団の中で過ごすお子さんのすぐそばで、直接的に関わりながら行う支援です。
主な支援内容は以下の通りです。
- 集団生活への参加サポート
活動の流れが分からず不安そうにしている時に「次〇〇する時間だよ」と声をかけたり、製作活動で手先がうまく使えない時に手伝ったりして、お子さんが集団の活動にスムーズに参加できるよう促します。 - 行動の観察とアセスメント
お子さんがどんな時に困り、どんなことに喜びを感じるのか、その行動の背景にあるものを専門的な視点でじっくりと観察し、より良い支援方法を探るための材料(アセスメント)を集めます。 - 学習や生活スキルの支援
授業についていくのが難しいお子さんには、集中できるような座席の工夫を提案したり、学習への意欲を引き出すような関わり方をしたりします。また、着替えや片付けといった生活スキルの向上もサポートします。 - 気持ちのコントロールやコミュニケーションの支援
お友達とぶつかってしまいがちな場面で間に入り、気持ちを代弁したり、自分の気持ちを伝える練習をしたりします。カッとなりやすいお子さんには、クールダウンできる場所を確保するなどの手伝いをします。
間接支援:先生や環境への働きかけ
お子さんが過ごしやすい環境を整えるために、担任の先生や周りの大人、クラス全体に働きかける支援です。こちらもお子さん本人にとって非常に重要なサポートです。
- 施設の職員へのアドバイス
「この子には、指示を出す時に絵カードを使うと伝わりやすいですよ」「褒めるときは、具体的に何が良かったのかを言葉にしてあげると自信につながります」など、担任の先生や保育士さんへ、お子さんの特性に合った効果的な関わり方を共有し、助言します。 - 環境の調整
音に敏感なお子さんのために教室の座席を静かな場所へ移動する、視覚的な情報が多いと混乱してしまうお子さんのためにパーテーションを置くなど、物理的な環境を調整する提案をします。 - 教材やツールの提案
コミュニケーションを助けるための絵カードやスケジュール表、気持ちを表現するためのツール、学習を支援するICT機器(タブレットなど)の活用方法などを具体的に提案します。 - クラス全体への働きかけ
お子さんがクラスに自然に溶け込めるよう、他の子どもたちに障害への理解を促すような活動を先生に提案するなど、クラス全体が温かい雰囲気で過ごせるような協力も行います。
支援の頻度と時間の目安
- 頻度:お子さんの状況によりますが、厚生労働省は2週間に1回(月に2回程度)の利用を標準的なモデルとして示しています。支援が必要な初期段階では回数を多くし、状況が安定してきたら月1回に減らすなど、柔軟に調整されます。
- 時間:1回の訪問時間は1時間~2時間程度が一般的です。例えば2時間の場合、「直接支援1時間+先生方との情報共有(カンファレンス)30分+保護者への報告30分」といったように、お子さんへの支援と関係者との連携をバランスよく行う時間配分が考えられます。
保育所等訪問支援を利用するまでの流れ【6ステップで解説】

「ぜひ利用してみたい!」と思ったものの、手続きが難しそう…と感じるかもしれません。
ここでは、利用開始までの一般的な流れを6つのステップに分けて解説します。
手続きの詳細は自治体によって異なる部分があるため、まずはお住まいの地域の窓口に確認することが大切ですが、大まかな流れを知っておくと安心です。
申請から利用開始までには、およそ1ヶ月~2ヶ月程度かかるのが一般的です。
【ステップ1】市区町村の窓口や相談支援事業所へ相談
まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(「障害福祉課」「子育て支援課」など名称は様々です)や、指定障害児相談支援事業所に「保育所等訪問支援を利用したい」と相談することから始まります。
【ポイント】
この時、事前にお子さんが通っている保育所や学校の担任の先生に「こういうサービスの利用を考えている」と一言伝えておくと、その後の連携がとてもスムーズに進むはずです。
【ステップ2】障害児支援利用計画案の作成
相談支援事業所の相談支援専門員が、保護者の方やお子さん本人と面談(アセスメント)の実施。
日頃の様子や困りごと、どんなサポートを希望するかなどを詳しくヒアリングし、サービスの必要性を判断します。必要と判断された場合、相談支援専門員が「障害児支援利用計画案」を作成してくれます。
【ステップ3】「通所受給者証」の申請と交付
ステップ2で作成された「障害児支援利用計画案」などの必要書類を添えて、市区町村の窓口にサービスの利用申請をしてください。
審査の結果、サービスの支給が決定されると、ご自宅に「通所受給者証」が郵送で届きます。この受給者証が、サービスを利用するための「許可証」のようなものです。
【注意】
すでに児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用していて受給者証を持っていても、「保育所等訪問支援」の利用については、改めて支給決定を受ける必要があります。
【ステップ4】保育所等訪問支援事業所との契約
利用したい保育所等訪問支援サービスを提供している事業所を探し、保護者と事業所との間で利用契約を結びます。どの事業所が良いか分からない場合は、相談支援専門員に相談してみましょう。
【ステップ5】個別支援計画の作成と担当者会議
契約後、今度は事業所の児童発達支援管理責任者(児発管)が中心となり、より具体的な支援内容を盛り込んだ「個別支援計画」を作成します。
この計画を作るにあたり、保護者、通っている園や学校の先生、相談支援専門員、事業所の担当者などが集まって「担当者会議」を開き、情報を共有し、支援の方向性を確認します。
関係者が同じ目標に向かってチームになるための、とても大切なプロセスです。
【ステップ6】支援開始とモニタリング
すべての準備が整ったら、いよいよ個別支援計画に基づいた訪問支援がスタートします。
支援はやりっぱなしではありません。少なくとも半年に1回以上は、支援が計画通りに進んでいるか、お子さんにとって効果的かを確認する「モニタリング」が行われ、必要に応じて計画の見直しが行われます。
イメージをつかむために、埼玉県さいたま市の事例をご覧ください。
👉総合療育センターひまわり学園|児童発達支援センター保育所等訪問支援
保護者の費用負担はどれくらい?
公的な福祉サービスと聞いても、やはり気になるのは利用料金。
保育所等訪問支援は、利用料の大部分を国と自治体が負担してくれるため、保護者の自己負担は大きく軽減されています。
原則1割負担
利用者は、サービスにかかった費用の原則1割を負担です。
具体的な金額は事業所によって異なりますが、1回あたり1,000円〜2,500円が目安となります。
世帯所得に応じた月額上限額
家計への負担が大きくなりすぎないように、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
この上限額は、保育所等訪問支援だけでなく、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、他の障害福祉サービスの利用料と合算した金額に適用されます。
| 世帯の所得状況 | 1ヶ月あたりの負担上限額 |
| 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満 ※) | 4,600円 |
| 上記以外(所得割28万円以上 ※) | 37,200円 |
※年収がおおむね900万円以下の世帯であれば、月に何度サービスを利用しても、自己負担は4,600円が上限となります。
関連記事👉放課後等デイサービスとは
幼児教育・保育の無償化も対象に
さらに、満3歳になって初めての4月1日から小学校に入学するまでの3年間のお子さんは、幼児教育・保育の無償化の対象となり、利用者負担額が0円になります。
このように、費用負担が心配で利用をためらう必要がないよう、様々な仕組みが整えられています。
申請に必要なものは?注意点もチェック
最後に、申請手続きの際に一般的に必要となる書類や、知っておきたい注意点について確認しておきましょう。
ただし、必要書類や様式は自治体によって異なるため、必ず事前にお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。
申請に必要となる主な書類
- 支給申請書:自治体の窓口で受け取ります。
- 障害児支援利用計画案:相談支援事業所が作成します。
- 世帯の所得を証明する書類:課税証明書など。
- マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカードや通知カードなど。
- お子さんの状態がわかるもの(※任意):医師の診断書や療育手帳、身体障害者手帳など。前述の通り、これらは必須ではありませんが、ある場合は提出を求められることがあります。
- 施設連絡承諾書など:訪問先の施設との連携を承諾する書類。
申請時の注意点
- 申請するのは「保護者」です
保育所等訪問支援の利用申請は、必ず保護者が行う必要があります。お子さんが通っている園や学校、あるいは訪問支援事業所が代行して申請することはできません。 - 訪問先(園や学校)の理解と協力が不可欠
このサービスは、訪問支援員が一方的に訪問するものではありません。日頃からお子さんの様子を見ている担任の先生方との連携が、支援の効果を大きく左右します。申請を進める前に、園や学校にサービスの利用について相談し、理解と協力を得ておくことが大切です。 - まずは窓口へ相談を!
手続きの流れや必要書類は、本当に自治体によって様々です。「どうすればいいんだろう?」と一人で悩まず、まずは第一歩として、お住まいの市区町村の担当窓口や相談支援事業所に電話をしてみることから始めましょう。
たとえば、とうきょう福祉ナビゲーションでは、東京都の事業所一覧が紹介されています。
とうきょう福祉ナビゲーション|保育所等訪問支援〔児童福祉法〕の一覧
インターネットで「保育所等訪問支援 〇〇県」と検索すると、お住まいの事業所が出てくるはずですので、積極的に調べてみてください。
保育所等訪問支援の解説:まとめ
保育所等訪問支援は、お子さんが「ふだん」の生活の場で、安心して自分らしく過ごし、成長していくための大きな力となる画期的なサービスです。
専門家がチームの一員として加わってくれることで、
- お子さん本人は、集団生活での「困った」が減り、自信を持って活動に参加できるようになります。
- 保護者の方は、専門的な視点からのアドバイスを得て、家庭での関わり方のヒントが見つかり、安心感につながります。
- 園や学校の先生方は、専門家と連携することで、お子さんへの理解を深め、より質の高い保育・教育を実践できます。
お子さんの集団生活での様子が気になったとき、「うちの子だけが違うんだろうか」と一人で抱え込まないでください。保育所等訪問支援は、そんなご家族と、お子さんを取り巻くすべての人々を支えるための制度です。
「もしかしたら、うちの子にも使えるかも?」
そう感じたら、ぜひお住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。

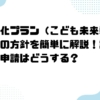
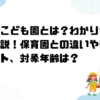

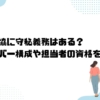
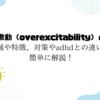
最近のコメント