懲戒権の削除について簡単に解説!見直しの理由やしつけのあり方を考える
懲戒権について、みなさんはどれくらいご存じでしょうか。
「子どもをしつけるために叩いた」
「言うことを聞かないから罰を与えた」
以前は、こうした行為が「しつけ」の一環として、ある程度許容される風潮があったことは事実です。
そして、その法的根拠の一つとされてきたのが、民法に定められていた懲戒権です。
しかし、2022年12月、この懲戒権を定めた条文は民法から削除されるという、歴史的な法改正が行われました。
なぜ、長年存在した懲戒権は削除されたのでしょうか?
懲戒権がなくなると、親は子どもに適切なしつけができなくなるのでしょうか?
これからの時代、私たちは子どもとどう向き合い、どう導いていけば良いのでしょうか?
この記事では、懲戒権の削除という大きな変化について、その背景や法改正のポイント、そして未来の子育てのあり方を、分かりやすく解説します。
児童虐待という深刻な問題から、学校でのルール、新しい時代の「しつけ」の考え方まで、網羅的に掘り下げて見ていきましょう!
関連👉こどもまんなか社会
懲戒権とは?明治時代から続いた親の権利
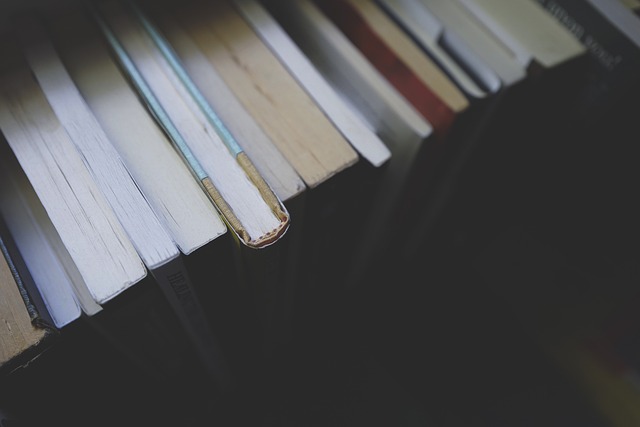
そもそも、今回削除された懲戒権とは、どのような権利だったのでしょうか。
まずはその定義と歴史的背景から見ていきましょう。
懲戒権は、改正前の民法第822条に定められていた、親権者が持つ権利の一つです※。
【旧民法第822条】
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
条文にある通り、「監護及び教育に必要な範囲内」で、親が子を「懲らしめ、戒める」ことが法的に認められていました。
この規定は1898年(明治31年)に施行された明治民法から引き継がれてきたもので、100年以上にわたり日本の親子関係における基本ルールの一つとされてきました。
この「懲戒」は、単に口で注意するだけでなく、子どもの過ちを正すための制裁的な意味合いを含むものと解釈されてきた歴史があります。
懲戒の具体例として「しかる、なぐる、ひねる、押し入れに入れる、禁食せしめる」といった、現代の感覚では明らかに虐待と捉えられる行為が挙げられていたことからも、その性質がうかがえます。
もちろん、時代とともに解釈は変化してきましたが、この懲戒権の存在が「しつけのためなら、ある程度の体罰は許される」という誤った認識の温床となり、後に深刻な問題へとつながっていくことになります。
参考|法務省|懲戒権に関する規定等の見直し
なぜ懲戒権は削除されたのか?背景にある深刻な児童虐待問題
100年以上も続いた懲戒権は、なぜこのタイミングで削除されることになったのでしょうか。
その最大の理由は、後を絶たない「しつけ」を口実とした児童虐待です。
「しつけのつもりだった」という言い訳
家庭という密室で起こる児童虐待事件において、加害者である親が「しつけのつもりだった」と主張するケースは実は珍しくありません。
民法に懲戒権という規定があることで、この言い訳に法的なお墨付きを与えかねない、という点が長年問題視されてきました。
親の「しつけ」という主張が壁となり、外部からの介入が遅れ、子どもの命が危険にさらされる。
そうした悲劇が繰り返される中で、「懲戒権は児童虐待を正当化する口実として悪用されている」という批判が、専門家や支援団体から強く上がっていました。
社会を揺るがした痛ましい事件
法改正への機運を一気に高める決定的な契機となったのが、2019年1月に千葉県野田市で発生した、小学4年生の女の子が父親から虐待を受けて死亡した事件です※。
父親による常軌を逸した暴力が「しつけ」という名の下に行われていた実態が明らかになり、社会全体に大きな衝撃と怒りをもたらしました。
この事件をきっかけに、「家庭内での体罰を法的に禁止すべきだ」という世論が急速に高まり、政治を大きく動かす力となったというのも背景の一つです。
国際社会からの厳しい目
懲戒権の見直しは、国内だけの問題ではありませんでした。
国連の「児童の権利委員会」は、日本の法律が体罰を明確に禁止しておらず、懲戒権の存在が体罰を許容しているかのように見える点を問題視し、日本政府に対して法改正を繰り返し勧告していました。
子どもの権利を国際基準で守るという観点からも、懲戒権の削除は避けて通れない課題となっていたわけです。
これらの国内の悲劇、世論の高まり、そして国際的な要請が一体となり、2019年の児童虐待防止法改正(親による体罰の禁止を明記)を経て、2022年の民法改正による懲戒権の削除へとつながっていきました。
参考|公益社団法人商事法務研究会|監護権の規定の在り方に関する研究会報告書(こちらの資料は「法務省・法制審議会 -民法(親子法制)部会」の資料として使用されています)
懲戒権の削除で何が変わった?新しい民法のルール
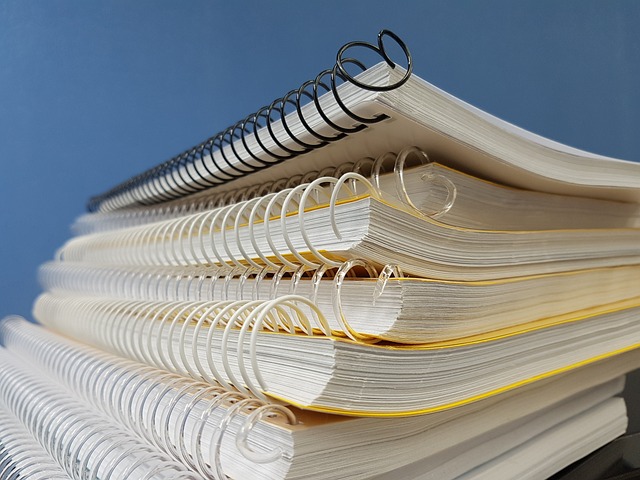
2022年12月16日に施行された改正民法では、懲戒権を定めた旧第822条が削除されるだけでなく、子どもの権利を尊重するための新しいルールが明確に定められました。
具体的に何がどう変わったのか、改正前と改正後を比較してみましょう。
| 改正前(旧民法) | 改正後(新民法) | |
| 第821条 | 子は、親権を行う者が定めた場所に、その居所を定めなければならない。(居所指定権) | 親権を行う者は、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 |
| 第822条 | 親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる。(懲戒権) | 【削除】 (条文自体が削除され、旧820条の内容が整理され、新しい822条として規定された)、親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 |
単に懲戒権がなくなっただけではない、という点が改正のポイントです。
- 子の人格の尊重義務を明記子どもは親の所有物や指導の対象ではなく、一人の独立した人格を持つ存在として尊重すべきである、という理念が国民の基本法である民法に初めて明記されました。
- 体罰等の禁止を明記これまで児童虐待防止法などで定められていた「体罰の禁止」が、民法にも明確に規定されました。さらに、殴る蹴るといった身体的な暴力だけでなく、「その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」も禁止対象に含まれています。これには、子どもの心を深く傷つける暴言なども含まれると解釈されています。
参考|法務省|懲戒権に関する規定等の見直し
厚生労働省|民法等改正に伴う児童福祉法等の改正について
正当なしつけはできなくなる? → そんなことはありません
この法改正を聞いて、「懲戒権がなくなったら、悪いことをした子どもをきちんと叱れなくなるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。
しかし、その心配は不要です。
今回の改正は、体罰や暴言に頼る不適切なしつけをなくすためのものであり、子どもの健やかな成長のために必要な指導を否定するものではありません。
社会的に許容される正当な範囲での指導やしつけは、これまで通り、民法第820条および新しい第822条に定められた親の「監護及び教育」の権利・義務として行うことができます。
重要なのは、その方法が「子の人格を尊重」し、「子の利益のため」になっているか、という点です。
「しつけ」と「体罰」の境界線はどこ?【具体例で解説】
出典:YouTube
厚生労働省公式チャンネルより
懲戒権が削除され、体罰が明確に禁止された今、すべての親にとって「しつけ」と「体罰」の違いを正しく理解することが、これまで以上に重要になっています。では、その境界線はどこにあるのでしょうか。
「しつけ」と「体罰」の定義
まず、それぞれの言葉の定義を確認しておきましょう。
- しつけとは子どもの人格や才能を伸ばし、社会で自律して生きていけるようにサポートする行為です。子どもの発達段階に応じて、社会のルールや望ましい行動を、本人が納得できるよう教えていくプロセスを指します。目的は子どもの成長を支えることにあります。
- 体罰とは親がしつけのためだと思ったとしても、子どもの身体に何らかの苦痛や不快感を引き起こす行為(罰)のことです。目的がどうであれ、手段として身体的な苦痛を用いた時点で体罰に該当します。
厚生労働省が公表しているガイドライン※では、具体例を挙げて分かりやすく解説しています。
※厚生労働省|体罰等によらない子育てのために
資料|子ども家庭庁|体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~(リーフレット)
これは体罰?それともOK?具体例でチェック
以下に挙げるのは、厚生労働省のガイドラインなどを参考に作成した具体例です。
【体罰に該当する行為の例】
- 何度も言い聞かせたのに言うことを聞かないので、頬を叩いた。
- 宿題をしなかったので、夕食を与えなかった。
- 大切なものにイタズラをした罰として、長時間正座させた。
- 友達を叩いたことを叱るために、同じように子どもを叩いた。
- 静かにしてほしくて、部屋の隅に立たせたままにする。
- 大声で繰り返し人格を否定するような暴言を浴びせた。
【体罰に該当しない行為の例】
- 道路に飛び出しそうになった子どもの腕を強く掴んで止めた。
- 他の子どもを叩こうとしたので、腕を押さえて制止した。
- 高いところに登って危ない子どもを、お尻を叩いて降ろした。(※罰ではなく、危険回避のための反射的な行為)
ポイントは、その行為が「子どもの身体や心を傷つける罰」なのか、それとも「危険を回避するためのやむを得ない制止」や「子どもの成長を促すための指導」なのか、という点です。
科学が証明する「体罰の有害性」
「愛のむち」という言葉がありますが、科学的には、体罰は「愛」でも「薬」でもなく、子どもの脳と心を傷つける「毒」であることが証明されています。
福井大学の友田明美教授らの研究によると、厳しい体罰や暴言といった不適切な養育(マルトリートメント)は、思考や理性を司る「前頭前野」や、言語理解に関わる「聴覚野」といった脳の部位を物理的に萎縮させることが分かっています。
体罰を受けた子どもは、受けなかった子どもに比べて、以下のような行動上の問題リスクが高まることも多くの研究で示されています。
- 攻撃的、反社会的になる
- 落ち着きがなく、集中力が続かない
- 自己肯定感が低くなる
- うつ病や不安障害などの精神的な問題を抱えやすくなる
- 親子関係が悪化する
体罰は、短期的には子どもを言うことを聞かせたように見えるかもしれませんが、長期的には子どもの健やかな発達を深刻に妨げる、百害あって一利なしの行為です。
学校における懲戒権はどうなる?教員の懲戒と体罰
家庭における親の懲戒権は削除されましたが、学校ではどうなのでしょうか。
結論から言うと、学校教育法第11条に基づき、校長および教員の懲戒権は引き続き存在しています。
【学校教育法第11条】
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
条文の最後に「ただし、体罰を加えることはできない」と明記されている通り、家庭と同じく、学校においても体罰は明確に禁止されています。
学校における「懲戒」と「体罰」の区別についても、文部科学省がガイドライン※で具体例を示しています。
| 分類 | 具体例 |
| 認められる懲戒(肉体的苦痛を伴わないもの) | ・放課後などに教室で反省させる<br>・授業中に教室の後ろなどで起立させる・学習課題や清掃活動などを課す・叱る、注意する |
| 体罰として禁止される行為 | ・生徒の頬を平手打ちする・背中を足で踏みつける・宿題を忘れた罰として、長時間正座で授業を受けさせる・トイレに行きたいと訴えても許可しない |
| 正当な行為(懲戒・体罰に当たらない) | ・他の生徒への暴力行為を制止するために腕をつかむ・危険な行為をした生徒を抑える |
ここでの重要な判断基準は、「肉体的苦痛を伴うかどうか」です。
例えば、放課後に教室に残すこと自体は懲戒として認められますが、その際に食事を与えなかったり、トイレに行かせなかったりすれば、それは肉体的苦痛を伴うため体罰と判断されます。
※文部科学省|体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)
体罰によらない子育てのあり方とは?
懲戒権が削除され、体罰に頼らない子育てが法的に明確化された今、私たち親や社会は、新しい子育てのあり方を模索していく必要があります。
それは「ポジティブ・ディシプリン(前向きなしつけ)」とも呼ばれるアプローチです。
罰によって子どもをコントロールするのではなく、子どもの権利を尊重し、肯定的な関わりを通じて、子どもの自律性や社会性を育んでいく考え方です。
ポジティブ・ディシプリンのポイント
- 子どもの気持ちに耳を傾けるなぜその行動をしたのか、子どもなりに理由があるはずです。まずは頭ごなしに叱るのではなく、「どうしてそうしたかったの?」と子どもの話に耳を傾け、気持ちを受け止めることが出発点です。
- 明確かつ具体的に、理由を添えて伝える「ダメ!」とだけ言うのではなく、「なぜダメなのか」「どうすれば良いのか」を、子どもの発達段階に合わせて分かりやすく説明します。「熱いから触るとヤケドして痛いよ」「お友達が悲しむから叩くのはやめようね」など、理由とセットで伝えることで、子どもは納得しやすくなります。
- 良い行動に注目し、褒める悪いことをした時だけ注目するのではなく、子どもが良い行動をした時にこそ、すかさず見つけて具体的に褒めることが大切です。褒められることで自己肯定感が育ち、望ましい行動が自然と増えていきます。
- 親自身がモデルになる子どもは親の姿を見て学びます。親が感情的に怒鳴ったり、暴力的な態度をとったりすれば、子どももそれを真似してしまいます。親自身が穏やかに、対話で問題を解決する姿を見せることが、何よりのしつけになります。
参考|Save The Children|ポジティブ・ディシプリン
リーフレットはこちらから!
懲戒権の削除について:まとめ
今回は、民法から懲戒権が削除された背景から、法改正の具体的な内容、そしてこれからのしつけのあり方までを詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 懲戒権の削除は、「しつけ」を口実とした児童虐待を防ぐための歴史的な法改正である。
- 改正民法では「子の人格尊重」と「体罰・暴言の禁止」が明確に定められた。
- 懲戒権がなくても、子の利益になる正当なしつけは可能。
- 体罰は子どもの脳と心を傷つける有害な行為であり、科学的にも証明されている。
- これからは罰ではなく、対話と肯定的な関わりで子どもの自律性を育む「ポジティブ・ディシプリン」が重要になる。
懲戒権の削除は、単なる法律の条文変更ではありません。
それは、子どもを親の管理対象ではなく、一人の独立した人格を持つ権利の主体として尊重するという、社会全体の価値観の転換をうながす、重要なメッセージです。
子育てに悩みはつきもの。
しかし、体罰に頼るのではなく、子どもの声に耳を傾け、根気強く向き合っていくことこそが、子どもの健やかな未来、そしてより良い社会を築くための確かな一歩となるはずです。
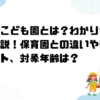
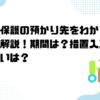


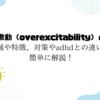
最近のコメント