一時保護の預かり先をわかりやすく解説!期間は?措置入所との違いは?
一時保護という言葉をニュースなどで耳にしたことはあっても、「具体的にどのような制度なの?」「もし保護されたら、子どもはどこで過ごすの?」と、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
子どもの安全が脅かされる緊急の事態において、命と心を守るために、一時保護は非常に重要な役割を果たします。
一方で、その実態はあまり知られていないのが現状です。
この記事では、そんな「一時保護」について、以下の点を中心に、誰にでも分かりやすく徹底解説します。
- 一時保護の目的と法的根拠
- 子どもはどこへ?多様な預かり先の詳細
- 保護される期間はどのくらい?
- 一時保護所での生活とは?
- よく似た「措置入所」との違い
この記事を読めば、一時保護制度の全体像を正しく理解し、子どもたちを取り巻く環境についてより深く知ることができるはずです!
関連記事👉児童相談所とこども家庭支援センター
そもそも「一時保護」とは?子どもの安全を守るための緊急措置

まずは、簡単に一時保護について見てみましょう。
虐待や育児放棄(ネグレクト)、保護者のいない状況など、子どもの福祉が著しく脅かされている緊急の場合に、子どもの安全を迅速に確保し、適切な保護を図るための制度のことです。
これは、児童福祉法第33条※に基づいて行われる、児童相談所長や都道府県知事等の権限による行政処分であり、あくまで緊急かつ暫定的な措置と位置づけられています。
一時保護の大きな特徴は、子どもの安全確保を最優先するため、保護者の同意がなくても実施できる点です。
これは、子どもの命を守るためには一刻の猶予もないケースがあるため、児童相談所長の職権によって行うことが法的に認められています。
令和4年の児童福祉法改正では※、一時保護の要件がより明確化され、「児童虐待のおそれがあるとき」などが法令上に明記されました。
参考|こども家庭庁|一時保護ガイドライン
※e-G0v法令検索|児童福祉法
※厚生労働省|一時保護の要件について
一時保護の3つの目的
一時保護は、主に以下の3つの目的で行われます。
- 緊急保護虐待やネグレクトなどから子どもを隔離する必要がある場合や、家出・迷子などで保護者がいない場合など、子どもの安全を緊急に確保します。子どもの行動が自身や他人に危害を及ぼすおそれがある場合も含まれます。
- 行動観察(アセスメント)子どもにとってどのような支援が最も適切か、その援助指針を定めるために、専門的な環境で一定期間、子どもの心身の状態、発達状況、行動などを詳しく観察します。
- 短期入所指導家庭から一時的に離れ、短期間のカウンセリングや生活指導などが子どもの状況改善に有効だと判断される場合に実施されます。
【一覧】一時保護の預かり先はどこ?一時保護所だけじゃない多様な選択肢
「一時保護」と聞くと、多くの方が「一時保護所」という施設を思い浮かべるかもしれません。
もちろん、一時保護所は中心的な役割を担っていますが、保護される子どもの預かり先はそれだけではありません。
子どもの年齢や心身の状態、個別の事情に応じて、最適な環境が選択されます。
中心的役割を担う「一時保護所」
一時保護の最も基本的な預かり先は、児童相談所に併設、もしくは密に連携可能な場所に設置されている一時保護所です。
全国に159箇所(令和7年4月現在)※あり、2歳から18歳未満の子どもたちが対象となります。
ここでは、専門の職員による24時間体制の見守りのもと、安全な環境で生活を送ります。
※こども家庭庁|児童相談所一覧
状況に応じて選択される「委託一時保護」
一時保護所での対応が難しい、あるいは、別の環境が望ましいと判断される場合には、児童相談所が適切な施設や個人に保護を委託する「委託一時保護」が行われます。
それぞれの施設の役割をざっと見てみましょう。
| 委託先の種類 | 主な対象となる子どもや状況 | 特徴 |
| 乳児院 | おおむね2歳未満の乳幼児 | 一時保護所では専門的なケアが難しいため、夜間の緊急保護でも乳児院が対応することが多い。 |
| 児童養護施設 | 専門的なケアが必要な子ども、一時保護所の定員超過時など | 既に施設に入所している子どもが別のケアを要する場合などにも活用される。 |
| 里親 | より家庭的な環境での養育が望ましいと判断された子ども | 養育経験が豊富な里親家庭で、落ち着いた生活を送ることができる。 |
| ファミリーホーム | 小規模な住居で家庭的な養育が必要な子ども | 養育者と5〜6人の子どもが共に生活する、より家庭に近い環境。 |
| 医療機関(病院) | 病気やケガの治療、医学的な管理が必要な子ども | 専門的な医療的ケアを受けながら保護される。 |
| 警察署 | 夜間や遠隔地で発生し、直ちに児童相談所へ引き継げない場合 | あくまでやむを得ない事情がある場合の一時的な保護委託。 |
| その他適当な者 | 児童委員、保育士、教員など | 児童福祉に深い理解と経験を持つ個人に委託される場合もある。 |
一口に「一時保護」と言っても、子どもの状況に合わせて非常に多様な預かり先が用意されているのがわかると思います。
とくに、専門的なケアが必要な乳児については、一時保護所ではなく乳児院や里親へ委託されるのが一般的です。
なお、一時保護については、ガイドラインの第5章に示されています。
詳細については、以下👇の「こども家庭庁」リンクを参照ください。
参考|厚生労働省|社会的養護の施設等について
参考|こども家庭庁|児童相談所運営指針の全部改正について:第5章 一時保護
一時保護される期間はどのくらい?原則と延長のルール

子どもの行動の自由を制限する措置であるため、一時保護の期間は、その目的を達成するために必要最小限でなければならないと定められています。
もう少し詳しく紹介します。
一時保護の原則は「2か月以内」
児童福祉法では、一時保護の期間は原則として2か月を超えてはならない※と明確に規定されています。
これは、保護の長期化による子どもへの心身の負担を防ぐための重要なルールのためです。
参考|こども家庭庁|児童相談所運営指針の全部改正について:第5章 一時保護
期間が延長されるケースもある
とはいえ、引き続き保護が必要であると児童相談所長などが判断した場合には、2か月を超えて一時保護を継続することが可能です。
しかし、その延長には手続きが求められます。
- 親権者等の同意がある場合: 児童相談所長等の判断で延長が可能です。
- 親権者等の意に反する場合(同意がない場合): 2か月を経過するごとに家庭裁判所の承認を得る必要性あり。
このように、司法の審査を導入することで、不当な保護の長期化を防ぎ、子どもの権利を守る仕組みが整えられています。
ちなみに、厚生労働省の調査によると、一時保護された子どもの実際の平均保護期間は30.3日です※。
しかし、全体の14.4%は2か月を超えており、その場合の平均保護期間は104.6日に及びます。
保護後の行き先となる施設や里親の不足などから、一時保護が長期化するケースも少なくなく、社会的な課題となっています。
※三菱UFJリサーチ&コンサルティング|令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業|一時保護所の実態と在り方及び一時保護等の手続の在り方に関する研究調査 報告書 p5
一時保護所ってどんなところ?子どもたちの生活環境
子どもたちが一時的に生活する一時保護所とは、一体どのような場所なのでしょうか。
その所在地は、子どもの安全確保の観点から公にされていないことがほとんどですが、子どもたちが安心して過ごせるよう、様々な配慮がなされています。
施設の概要と対象年齢
一時保護所は、児童相談所に併設、または連携しやすい場所にあり、その設備や運営の基準は児童養護施設に準じています。全国に159か所あり、定員は合計で3,219名です(令和7年4月現在)。
対象となる子どもの年齢は、おおむね2歳から18歳未満です。前述の通り、2歳未満の乳幼児は、専門的なケアが可能な乳児院や里親に委託されることが一般的です。
関連サイト👉子ども家庭庁|児童相談所一覧(全国・一時保護所情報も含む)
一時保護所での生活
一時保護所では、子どもたちが規則正しく、安定した生活を送れるような環境が整えられています。
- 設備: 居室、食堂、お風呂、トイレといった基本的な生活設備のほか、体育館や運動場、図書室などが備えられている施設もあります。
- 生活の流れ: 専門の職員が24時間体制で子どもたちを見守り、起床から就寝まで、日課に沿った集団生活を送ります。食事や入浴の時間も決められています。
- 学習・活動: 保護されている間、原則として学校に通うことはできません。しかし、学習の遅れが出ないよう、所内で職員による学習指導が行われたり、保育プログラムやレクリエーション活動が実施されたりします。
生活上の制限とその理由
安全を確保し、子どもを混乱から守るため、一時保護所での生活にはいくつかの制限があります。
例えば、外部との連絡(電話や手紙)、家族との面会、私物の持ち込みなどが制限されることがあります。
これらの制限は、子どもを傷つける可能性のある外部からの接触を断ち、心身を休ませるための重要な措置です。
しかし、近年では子どもの権利擁護の観点から、画一的な制限を見直し、個々の子どもの状況に応じた柔軟な対応の必要性が議論されています。
「一時保護」と「措置入所」の決定的な違いとは?

一時保護と並んで、児童相談所が行う子どもの保護に関する手続きに「措置入所(そちにゅうしょ)」があります。
この二つは混同されがちですが、その目的や性格は全く異なるものです。
簡単に言えば、一時保護は「救急外来での応急処置」、措置入所は「専門病棟への入院治療」に例えることができます。
| 項目 | 一時保護 | 措置入所 |
| 法的根拠 | 児童福祉法 第33条 | 児童福祉法 第27条、第28条 |
| 性格・目的 | 緊急・暫定的な安全確保、状況把握(アセスメント) | 恒久的・継続的な養育、保護、自立支援 |
| 期間 | 原則2か月以内(延長には家裁の承認が必要な場合も) | 期間の定めなし(長期的な生活が前提) |
| 親権者の同意 | 不要(児童相談所長の職権で可能) | 原則として必要(同意がない場合は家庭裁判所の承認が必要) |
| 主な場所 | 一時保護所、委託先(乳児院、里親など) | 児童養護施設、乳児院、里親家庭など |
一時保護は、あくまで危険から子どもを緊急避難させ、今後の支援方針を決めるための「入口」と考えてください。
そして、一時保護での観察や調査を経て、家庭に戻るのが難しいと判断された場合に、児童養護施設や里親家庭といった長期的な生活の場を確保する「措置入所」へと移行するのが一般的な流れとなります。
一時保護が必要な時の相談窓口
「虐待かも…」と思ったり、子育てに悩んで追い詰められたりしたとき、一人で抱え込む必要はありません。
ためらわずに専門の窓口に相談することが、子どもの未来を守る第一歩になります。
【児童相談所虐待対応ダイヤル】
電話番号:189(いちはやく)
- 24時間365日対応
- 通話料無料
- お近くの児童相談所につながります
- 相談・通告は匿名で行うことも可能です
「確信がないから…」とためらう必要はありません。
気がついた人からの1本の電話が、子どもを救うきっかけになるかもしれません。
関連サイト👉子ども家庭庁|児童相談所一覧(全国・一時保護所情報も含む)
一時保護の預かり先について:まとめ
今回は、子どもの命と未来を守るための重要なセーフティネットである「一時保護」について、その預かり先や期間、措置入所との違いなどを詳しく解説しました。
- 一時保護は、子どもの安全を確保するための緊急・暫定的な措置である。
- 預かり先は一時保護所だけでなく、乳児院や里親など、子どもの状況に応じて様々である。
- 期間は原則2か月以内で、延長には厳格なルールが定められている。
- 一時保護は緊急避難、措置入所は長期的な養育と、目的が明確に異なる。
一時保護は、子どもにとっても、そして保護者にとっても、人生の大きな転機となり得ます。
この制度がなぜ必要なのか、そしてどのような仕組みで運用されているのかを社会全体で正しく理解し、困難を抱える子どもや家庭を温かく見守る意識を持つことが、何よりも大切なのではないでしょうか。
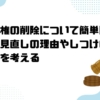


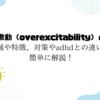
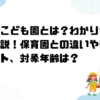

最近のコメント