加速化プラン(こども未来戦略)の方針を簡単に解説!課題は?申請はどうする?
「こども未来戦略」に基づく、加速化プランが2025年度から本格的に始動し、子育て支援が大きく変わろうとしています。
「制度が多すぎてよくわからない」
「自分はどの支援を受けられるの?」
そんな疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、国の新しい子育て支援策の中核である「こども・子育て支援加速化プラン」について、わかりやすく徹底解説します。
拡充される支援内容や具体的な申請方法、そして課題まで、網羅的にご紹介します。
この記事を読めば、新しい制度を正しく理解し、ご自身の家庭に合った支援を見つけるための第一歩を踏み出せるはずです!
こども・子育て支援加速化プランとは?未来への投資の全体像
出典:YouTube:こども家庭庁公式チャンネル
まず、今回の政策の核となる「こども・子育て支援加速化プラン」の全体像をつかみましょう。
これは、2024年度から2026年度までの3年間で集中的に実施される政策パッケージです。
2022年の出生数は77万人を割り込み過去最少を更新するなど、日本の少子化は待ったなしの状況と言われています※。
この国家的危機に対し、政府は総額3.6兆円規模という前例のない予算を投じ、子育て世帯を強力にサポートする姿勢を明確にしました※。
加速化プランは、以下の4つの大きな柱で構成されています。
- ライフステージを通じた経済的支援の強化と若い世代の所得向上: 児童手当の拡充や教育費の負担軽減など、子育て世帯の家計を直接的に支援。
- 全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充: 妊娠期から切れ目なく、保育の質の向上や、多様なニーズ(貧困・虐待・障害など)に対応できる支援基盤を強化。
- 共働き・共育ての推進: 男性の育休取得を後押しし、男女が共に育児とキャリアを両立できる社会を目指すための制度を整えます。
- こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革: 「こどもまんなか社会」の実現に向け、社会全体で子育て世帯を支える雰囲気作り。
これらの施策を通じて、経済的な理由で子どもを持つことを諦める世帯を減らし、誰もが安心して子どもを産み育てられる社会を目指すのが「加速化プラン」の大きな目標です。
※厚生労働省|令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況
※こども家庭庁|2025年4月からいよいよ本格始動。「こども・子育て支援加速化プラン」とは?
2025年度から本格始動!加速化プランの主要な支援策を徹底解説
出典:YouTube:こども家庭庁公式チャンネル
2025年4月から、加速化プランの多くの施策が本格的にスタートしました。
ここでは、特に影響の大きい主要な支援策を「経済的支援」「共働き・共育て支援」「保育・通園支援」の3つのカテゴリーに分けて、具体的に見ていきましょう。
経済的支援の強化:家計に直結する嬉しい変更点
子育て世帯の家計負担を直接的に軽減するための支援が大幅に拡充されます。
大きなポイントを、わかりやすく表にまとめました。
| 支援制度 | 概要 | ポイント |
| 児童手当の抜本的拡充 | 所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長。第3子以降は月額3万円に増額。 | ・2024年10月分から適用・支給回数が年3回→年6回(偶数月)に・多子加算の対象が22歳年度末までに拡大 |
| 高等教育費の負担軽減 | 扶養する子どもが3人以上いる多子世帯を対象に、所得制限なしで大学等の授業料・入学金を無償化。 | ・2025年度から開始・大学院修士課程向けの授業料後払い制度も導入 |
| 妊婦のための支援給付 | 妊娠・出産時に合計10万円相当の経済的支援を行う「出産・子育て応援交付金」を制度化。 | ・妊娠届出時に5万円相当・出生届出時に5万円相当 |
共働き・共育ての推進:働きながら育てる環境を整備
男女が共に育児に参加し、キャリアを継続できる社会を目指すための新しい給付制度が創設されました。
| 支援制度 | 概要 | ポイント |
| 出生後休業支援給付 | 子の出生後8週間以内に両親が共に14日以上の育休を取得した場合、最大28日間、手取り10割相当を給付。 | ・2025年4月から開始・男性の育休取得を強力に後押し |
| 育児時短就業給付 | 2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択し賃金が低下した場合、低下した賃金の10%を給付。 | ・2025年4月から開始・時短勤務による収入減をカバー |
| 柔軟な働き方の義務化 | 3歳から小学校就学前の子を持つ従業員に対し、事業主がテレワークや時短勤務など複数の働き方を選択できる制度を設けることを義務化。 | ・2025年10月から開始 |
保育・通園支援の拡充:多様なニーズに対応
保育サービスの質的・量的な拡充も進められます。
| 支援制度 | 概要 | ポイント |
| こども誰でも通園制度 | 親の就労要件を問わず、月一定時間まで子どもを保育所などに預けられる制度。 | ・2026年4月から全国で本格実施予定・保護者のリフレッシュや急な用事にも対応 |
| 保育の質の向上 | 保育士の配置基準を改善し、より手厚い保育を実現。 | ・2025年度から1歳児クラスで保育士1人あたりの子どもが6人→5人に改善 |
こども家庭庁|こども未来戦略 加速化プラン|こども・子育て支援|2025年4月から さらに充実します
をもとに作成。
【どうすればもらえる?】加速化プランの各種支援策の申請方法
ここまで、加速化プランについてのポイントを解説しました。
とはいえ、新しい支援策を実際に利用するためには、制度ごとに定められた申請手続きが必要です。
手続きの方法は大きく3つのパターンに分かれます。
ご自身が利用したい制度がどれに該当するか確認しましょう。
1. 個人が市区町村に直接申請するケース
もっとも一般的なのが、お住まいの市区町村の窓口で個人が手続きを行うパターンです。
- 対象となる主な支援:
- 児童手当: 新たに高校生年代の子どものみを養育する世帯や、これまで所得上限超過で受給していなかった世帯などは申請が必要です。既に受給中の多くの世帯は手続き不要ですが、念のため自治体のホームページ等で確認しましょう。
- 妊婦健康診査費用補助: 妊娠届を提出する際に、母子健康手帳とあわせて補助券が交付されます。
- 申請先: 住民票のある市区町村の役場(子育て支援課など)
- ポイント: 制度によって申請期間が定められている場合があります。特に児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となるため、対象となる方は早めに手続きを行いましょう。
例として、さいたま市の子育て支援課のリンクを紹介します。
👉さいたま市|こそだて支援課
2. 事業者・機関経由で手続きが行われるケース
勤務先や契約する事業者を通して手続きが進められるパターンです。
個人が直接行政に申請するわけではないため、まずは関連する事業者への確認が第一歩となります。
- 対象となる主な支援:
- 共働き・共育て関連給付(出生後休業支援給付、育児時短就業給付): 雇用保険に基づく給付のため、原則として勤務先の事業主を通じてハローワークに申請します。まずは会社の人事・労務担当部署に相談してください。
- 高等教育の修学支援新制度: 在学している大学や専門学校の窓口を通じて、日本学生支援機構(JASSO)に申し込みます。
- 住宅関連支援(子育てエコホーム支援事業など): 補助金は、国に登録された住宅メーカーや工務店などの「エコホーム支援事業者」が申請手続きを代行します。利用したい場合は、登録事業者と契約する必要があります。
- ポイント: 勤務先や学校、契約業者などが手続きの窓口となります。制度を利用したい旨を早めに伝え、必要な書類などを確認することが重要です。
👉全国のハローワーク所在地(リンク)
👉日本学生支援機構(リンク)
いずれの制度を利用するにしても、まずは「自分が対象かどうか」を確認し、「どこが申請窓口か」を把握することが最も重要です。
不明な点は、市区町村の窓口や勤務先に遠慮なく問い合わせましょう。
期待と不安が交錯する「加速化プラン」の5つの課題
加速化プランは子育て世帯にとって大きな希望となる一方、その実現には多くの課題も指摘されています。
ここでは、知っておくべき5つの主要な課題について解説します。
加速化プランの課題1:財源確保と「子ども・子育て支援金」への批判
約3.6兆円という巨額の財源をどう確保するのかは、最大の論点です。
そのうち約1兆円は、2026年度から創設される「子ども・子育て支援金」で賄う計画ですが、これには厳しい意見が寄せられています。
- 実質的な負担増: 政府は「実質負担なし」と説明しますが、公的医療保険料に上乗せされる形で、新たな負担が発生します。
- 「独身税」との批判: 子どもがいない世帯や独身者にも負担が課される構造に対し、不満の声も。
- 現役世代への偏重: 負担の多くを現役世代が担うため、結果的に子育て世帯自身の手取りが減少するという矛盾も指摘されています。
【子ども・子育て支援金の負担額目安(月額・被保険者一人あたり)】
| 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | |
| 被用者保険(会社員など) | 450円 | 600円 | 800円 |
| 国民健康保険(自営業者など) | 350円 | 450円 | 600円 |
| 後期高齢者医療制度(75歳以上) | 200円 | 250円 | 350円 |
参考|MUFG|子育て支援金とは?子ども・子育て支援法改正の内容をわかりやすく解説!
加速化プランの課題2:保育現場の深刻な人手不足
保育士の配置基準改善は素晴らしい目標ですが、それを担う保育士が足りていません。
保育士の有効求人倍率は全職種平均を大幅に上回っており、「給料が安い」「仕事量が多い」といった構造的な問題が未解決のままでは、基準を満たすための人材確保は困難です。
加速化プランの課題3:「こども誰でも通園制度」の懸念点
親の就労を問わない「こども誰でも通園制度」は画期的ですが、試行段階で課題が浮上しています。
- 安全性と質の確保: 環境に慣れない子どもを短時間で受け入れることによる事故リスクの増加や、既存園児への影響が懸念されています。
- 保育士の負担増: 通常の保育に加えて新たな対応が必要となり、現場の疲弊が心配されます。
- 制度設計の問題: 月10時間という利用時間では効果が限定的であることや、財政面の不安定さも指摘されています。
加速化プランの課題4:政策効果への疑問と制度間の不整合
そもそもこれらの施策が本当に「少子化トレンドの反転」につながるのか、という根本的な疑問も。
- 目標設定の曖昧さ: 何をもって「トレンドが反転した」とするのか、具体的な目標や検証方法が不明確です。
- 支援の偏り: 第3子以降への手厚い支援に比べ、多くの家庭が直面する「第一子の壁」を乗り越えるための支援が十分とは言えません。
- 働き方改革との乖離: 長時間労働が常態化している職場環境が変わらなければ、いくら育休制度を整えても「共働き・共育て」は絵に描いた餅になりかねません。
加速化プランの課題5:解消されない地域間格差
子育て支援のインフラが不足している地方と、待機児童問題が依然として深刻な都市部とでは、抱える課題が異なります。全国一律の政策だけでは、こうした地域ごとの実情に対応しきれず、政策効果が限定的になる可能性があります。
加速化プランの解説まとめ:こども未来戦略の成功に向けて私たちができること
今回は、こども未来戦略の新たな政策である「こども・子育て支援加速化プラン」について解説しました。
本政策は、子育て世帯の経済的・時間的負担を軽減し、未来への希望を育むための重要な一歩です。
児童手当の拡充や新たな育休給付など、多くの家庭にとって具体的なメリットがあることは間違いありません。
しかし、その一方で、財源の問題や現場の人手不足、制度設計上の課題など、乗り越えるべきハードルが山積しているのも事実です。
この戦略を成功に導くためには、政府の取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの関心と行動が不可欠です。
- まずは「知る」こと: ご自身の家庭がどの支援の対象になるのかを正しく理解し、利用できる制度は積極的に活用しましょう。
- 地域の情報にアンテナを張る: 自治体独自の支援策や、お住まいの地域の保育事情など、身近な情報に関心を持つことが大切です。
- 社会全体で考える: 子育ては、親だけが担うものではありません。未来を担う子どもたちを社会全体でどう支えていくか。このプランをきっかけに、家族や地域、職場で話し合ってみることも、大きな一歩となるはずです。
「こどもまんなか社会」の実現は、まだ始まったばかりです。
課題を直視しつつ、新しい支援制度を賢く活用し、より良い未来を築いていきましょう。

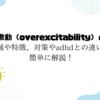


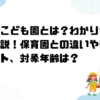

最近のコメント