自立支援協議会(自立協)を簡単に解説!メンバーや6つの機能、活動内容や位置づけは?
「自立支援協議会」という言葉をご存じですか?
福祉関係の仕事に携わっている方や、障害のあるご家族がいる方でなければ、あまり馴染みのない言葉かもしれません。
「一体何をするための組織なの?」
「どんな人が参加していて、どんな活動をしているの?」
今回は、そんな疑問をお持ちの方のために、障害のある方の地域生活を支える重要な機関である「自立支援協議会」について、その全体像を分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、自立支援協議会の位置づけや目的、具体的な活動内容、そしてそれを支えるメンバー構成まで、網羅的に理解することができます。
関連記事👉要対協とは
自立支援協議会とは?

まずは、自立支援協議会について簡単に説明します。
自立支援協議会とは、障害のある方が、地域で安心して生活できる社会を実現するために設置される、地域の支援体制の中核を担う協議の場です。
根拠となる法律は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」で、その第89条の3※に基づいて、市町村または都道府県に設置することが「努力義務」とされています。
つまり、法律で設置が推奨されている公的な機関です。
協議会の最大の目的は、地域のさまざまな関係者が顔を合わせ、連携することにあります。
福祉、保健、医療、教育、就労といった各分野の専門家や、障害のある当事者・そのご家族、地域住民などが集まり、個別の支援に関する課題から、地域全体の制度的な課題までを共有し、解決策を一緒に考えていきます。
「人と人をつなぎ、地域の課題を地域で共有し、解決に向けて協働する」ための司令塔と理解していただくと良いかもしれません。
※e-gov法令検索|障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律|第八十九条の三
参考|厚生労働省|(自立支援)協議会について
自立支援協議会の位置づけ|市町村と都道府県の役割の違い
自立支援協議会は、市町村と都道府県の両方に設置されますが、それぞれで担う役割や視点が異なります。ここでは、その位置づけと役割の違いについて見ていきましょう。
法律上の位置づけと法定化の経緯
自立支援協議会は、もともと2006年施行の障害者自立支援法で地域生活支援事業の一つとして位置づけられていました。その後、運営の活性化を図るため、2012年(平成24年)4月の法改正で法律上の位置づけが明確にされ、「法定化」されました。
現在、市町村協議会は全国の98%※(令和4年度時点)、都道府県協議会は全ての都道府県に設置されており、障害福祉に欠かせない重要な機関として全国に根付いています。
参考|厚生労働省|(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン(改定版),p4(令和7年5月)
市町村における自立支援協議会の役割
市町村に設置される協議会は、住民にとって身近な生活圏域における支援体制の中核を担います。
日々の相談支援業務などを通じて明らかになった、個別の具体的な支援事例(「Aさんのようなケースでは、地域にこんなサービスがあれば…」など)をきっかけに、そこに潜む地域全体の課題を抽出します。
そして、その課題を解決するため地域の関係者が協力し、地域の福祉サービス基盤の整備を着実に進めていく役割を持っています。
そのような意味において、まさに、地域づくりの最前線と言えるかもしれません。
都道府県における自立支援協議会の役割
一方、都道府県に設置される協議会は、より広域的な視点から、都道府県全体の支援体制の整備をリードする役割を担います。
市町村をまたぐような広域的な課題への対応や、市町村協議会の後方支援が主な役割です。
例えば、相談支援を担う専門職の人材確保や養成方法の検討、障害者虐待の防止や早期発見に向けた体制づくりなど、一つの市町村だけでは解決が難しい大きなテーマに取り組みます。各市町村協議会と連携を取りながら、県全体の支援の質を向上させるための主導的な役割を果たしていると言えるでしょう。
参考|財団法人日本障害者リハビリテーション協会|都道府県自立支援協議会の機能と役割|自立支援協議会のあり方を探る
自立支援協議会の6つの機能

自立支援協議会は、地域課題を解決するために、大きく分けて6つの重要な機能を持っています。
これらの機能はそれぞれ独立しているのではなく、互いに連携し、影響し合うことで総合的な力を発揮します。
- 情報機能
- 調整機能
- 開発機能
- 教育機能
- 権利擁護機能
- 評価機能
一つずつ見ていきましょう。
参考|一般社団法人北海道総合研究調査会|(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン(案),p5
自立支援協議会の6つの機能① 情報機能(情報の共有と発信)
協議会の最も基盤となるのが情報機能です。
個々の支援者が抱える困難な事例や、地域に埋もれているニーズといった「潜在的な情報」を、協議会の場に持ち寄って共有し、「顕在化(見える化)」させます。
プライバシーに配慮しながら情報を集約・共有することで、関係者全員が「地域で何が課題なのか」を理解し、議論を始めることができます。
また、地域の福祉サービスなどの情報をまとめた資源マップを作成・発信し、必要な人が必要な情報にアクセスしやすくする役割も担います。
自立支援協議会の6つの機能② 調整機能(ネットワークの構築と連携)
障害のある方の生活課題は、福祉だけで解決できるとは限りません。保健、医療、教育、就労、住まいなど、さまざまな分野の支援が不可欠です。
調整機能は、これらの分野の垣根を越えたネットワークを構築し、関係機関がスムーズに連携できるよう「調整」するのも重要な役割です。
例えば、ある一人の困難事例に対して、関係者が集まる「個別支援会議」を開き、それぞれの専門性を活かした役割分担を決め、チームとして支援にあたります。このような活動を通じて、普段は接点のない機関同士が「顔の見える関係」を築き、いざという時に協力し合える強固な連携体制(ネットワーク)を作り上げていきます。
自立支援協議会の6つの機能③ 開発機能(社会資源の開発・改善)
地域の課題を共有し、話し合いを進める中で、「既存のサービスでは対応できない」「そもそも地域にこういう仕組みが足りない」といったニーズが明らかになります。
開発機能は、こうした地域に不足している社会資源(サービスや制度、活動の場など)を新たに「開発」したり、既存の資源をより良く「改善」したりする機能です。
まさに「ないなら、つくろう」という発想で、地域のニーズに応える新しいサービスや支援の仕組みを創出します。
例えば、医療的ケアが必要な子どもたちのための支援体制の構築や、新たな日中活動の場の設置などがこれにあたります。
自立支援協議会の6つの機能④ 教育機能(人材育成と資質向上)
自立支援協議会は、参加する支援者自身の専門性や資質を向上させる「学び合いの場」としての機能も持っています。
先進的な取り組み事例を共有する勉強会や、新しい制度に関する研修会などを企画・実施することで、地域の支援者全体のスキルアップを図ります。
これにより、地域全体の支援の質を高め、より良いサービス提供につなげることを目指します。
自立支援協議会の6つの機能⑤ 権利擁護機能(権利を守り、安心して暮らせる地域づくり)
障害のある方が差別や権利侵害を受けることなく、その人らしく尊厳を持って生活できる地域や仕組みを作るための機能です。
具体的には、障害者虐待の未然防止、早期発見・早期対応に向けた体制づくりに関する協議や、障害を理由とする差別の解消に向けた啓発活動などを行います。
当事者の「こうしたい」というニーズの実現を支え、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指す、非常に重要な機能です。
自立支援協議会の6つの機能⑥ 評価機能(活動を振り返り、次へつなげる)
協議会の活動や地域の福祉サービスが、きちんと機能しているか、質の高いものになっているかを中立・公平な立場で「評価」し、改善を促す機能です。
例えば、市町村から委託された相談支援事業所の運営状況を評価したり、基幹相談支援センターの事業実績を検証したりします。
活動のプロセスや成果を客観的に分析し、「やりっぱなし」にせず、次の課題解決やさらなる改善へとつなげていく、PDCAサイクル※を回すための重要な役割を担っています。
PDCAサイクル・・・PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取ったもの。運用やマネジメントを最適にするための行動順序を記した造語。
具体的に何をしている?自立支援協議会の活動内容
では、6つの機能を果たすために、自立支援協議会では具体的にどのような活動が行われているのでしょうか。市町村と都道府県、それぞれの主な活動内容と、それを支える会議の仕組みを見ていきましょう。
市町村自立支援協議会の主な活動内容
住民に身近な市町村協議会では、以下のような実践的な活動が中心となります。
- 個別事例への支援のあり方に関する協議・調整:支援が困難なケースについて関係者が集まり、具体的な支援方針を話し合う。
- 地域における課題の抽出・把握・共有:個別事例の検討から見えてきた地域共通の課題を明らかにする。
- 社会資源の開発・改善:地域の課題解決に必要な新しいサービスや仕組みづくりを検討・提案する。
- 地域の関係機関の連携強化:定例会や研修会を通じて、顔の見える関係づくりを進める。
- 障害福祉計画への助言:市町村が策定する障害福祉計画に対し、現場の視点から意見を述べる。
- 障害者虐待防止のための体制構築に関する協議。
- 地域の課題を都道府県協議会へ報告する。
参考出典:YouTube:東松山市地域自立支援協議会普及・啓発プロジェクト動画より
都道府県自立支援協議会の主な活動内容
広域的な視点を持つ都道府県協議会では、市町村を支え、県全体の体制を整えるための活動が中心です。
- 都道府県内の支援体制に関する課題の共有:市町村から報告された課題などを集約し、県全体の課題を把握する。
- 相談支援従事者の人材確保・養成方法の協議:専門職のスキルアップ研修のあり方などを検討する。
- 広域的な社会資源の開発・改善。
- 市町村協議会への助言やサポート。
- 都道府県障害福祉計画の進捗状況の把握と助言。
参考出典:YouTube:岸和田市自立支援協議会PRより
自立支援協議会の仕組み(代表者会議・専門部会など)
自立支援協議会は、効率的・効果的に議論を進めるため、多くの場合、目的やテーマに応じて階層的な組織構造を持っています。
事例ウェブサイト1
- 個別支援会議:協議会の活動の原点。特定の個人の支援について、必要な関係者が集まり具体的な支援方針を協議します。ここでの気づきが、地域課題発見の出発点となります。
- 専門部会・分科会:「就労支援」「子育て支援」「権利擁護」など、特定のテーマごとに設置されます。現場の実務者が中心となり、具体的な課題解決策を深く検討します。
- 運営会議・事務局会議:各部会での協議内容を整理し、協議会全体の進行管理や運営実務を担う、いわば実働部隊です。
- 代表者会議:関係機関の代表者で構成される、協議会の最高意思決定機関。各部会からの提案を承認したり、協議会全体の運営方針を決定したりします。
このように、現場レベルの小さな会議から、地域全体の大きな方針決定まで、有機的に連携しながら活動が進められています。
どんな人が参加している?自立支援協議会のメンバー構成
自立支援協議会は、特定の分野の専門家だけで構成されるわけではなく、さまざまなメンバーで構成されています。
標準的な構成メンバー
メンバーは地域の実情に応じて選ばれますが※、一般的には以下のような関係者が参加しています。
- 相談支援事業者
- 障害福祉サービス事業者(障害児通所支援事業者も含む)
- 保健・医療関係者(医師、看護師、保健師など)
- 教育関係機関(特別支援学校、地域の小中学校など)
- 雇用関係機関(ハローワーク、障害者就業・生活支援センターなど)
- 権利擁護支援関係者(弁護士、社会福祉士会など)
- 企業、居住支援関係者
- 障害者関係団体、障害のある当事者及びそのご家族
- 民生委員、地域住民
- 学識経験者
- 行政職員(市町村・都道府県)
このように、福祉の専門家だけでなく、医療、教育、雇用、そして何よりもサービスの受け手である当事者や家族が加わることで、机上の空論ではない、実態に即した議論が可能になります。
※参考例|埼玉県自立支援協議会
メンバーの選定方法と当事者参画の重要性
メンバーは、行政が選任する場合もありますが、形式にこだわらず、課題解決に積極的に取り組める人材や、地域で信頼されている人材が柔軟に選ばれることが重要視されています。
特に重要なのが「当事者参画」です。
実際にサービスを利用する障害のある当事者やその家族が協議会に参加し、意見を述べることが、本当に必要とされる支援を生み出す上で不可欠です。
データによると、市町村協議会の74.5%に障害当事者団体・当事者が参加しており、当事者と共に地域づくりを進めていくという考え方が広く浸透しています。
関連記事👉要対協について
自立支援協議会についての解説:まとめ
今回は、障害のある方の地域生活を支える中核機関である「自立支援協議会」について、その位置づけから6つの機能、具体的な活動内容やメンバー構成までを詳しく解説しました。
最後に、この記事のポイントを振り返ります。
- 自立支援協議会は、障害者総合支援法に基づき、障害のある方の地域生活を支えるために市町村・都道府県に設置される協議の場。
- 市町村協議会は身近な地域の課題解決を、都道府県協議会は広域的な体制整備と後方支援を担う。
- 「情報」「調整」「開発」「教育」「権利擁護」「評価」**という6つの機能が連携し、地域課題の解決を目指す。
- 活動は、個別支援会議を原点とし、専門部会や代表者会議など階層的な会議体で進められる。
- メンバーは、福祉・医療・教育・雇用など多分野の関係者に加え、当事者・家族の参画が非常に重要視されている。
自立支援協議会は、一つの機関だけでは解決できない複雑な課題に対して、地域全体で取り組むための「チームづくりの要」です。もしこの記事を読んで興味を持たれたら、ぜひ一度、お住まいの市町村のホームページなどで、自立支援協議会の活動を調べてみてはいかがでしょうか。
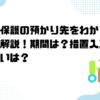


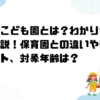

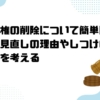

最近のコメント