ギフテッド教育をわかりやすく解説!メリット・デメリット、日本の現状は?
この記事では、ギフテッド教育についてわかりやすく解説します。
「周りの子と少し違う」「特定の分野で飛び抜けた才能を見せる」
そんな子どもに気づいたとき、どのような教育が必要でしょうか?
日本でも最近ようやく注目され始めた「ギフテッド教育」は、特別な才能を持つ子どもたちを支える重要な取り組みです。
しかし、まだ制度や環境が整っているとは言えず、保護者や教育関係者の中でも戸惑いや誤解が多いのが現状です。
この記事では、「ギフテッドとは何か?」から始まり、教育の現状、メリット・デメリット、実際の自治体の取り組みまでをわかりやすく丁寧に解説します。
詳細な情報については、可能な限り一次情報のリンクを添付しています。
関心のある方は、外部リンクも参考にしてください!
そもそもギフテッドとは?

ギフテッドの定義と背景
「ギフテッド(Gifted)」とは、知性、創造性、芸術性、リーダーシップ、特定の学問、運動能力といった特定の分野で、平均をはるかに超える才能を持つ子どもたちを指す用語です。
ただ、2025年5月現在では、統一された定義はまだありません。
IQあるいはIQ(知能指数)を構成する下位指標で130以上を基準とする傾向もあります。しかし、傾向としてはIQだけで判断されるわけではなく、「学ぶスピードが速い」「深く考える力がある」「強い探究心を持つ」といった特性も含みます。
このような特性の背景に過度激動(overexcitability)という特徴があり、通常は自然に受け入れる物事に対して過剰に反応し、その結果、日常にある矛盾に気づきやすく、それを探求するモチベーションを持つとも考えられています。
特定の分野でかなり高い能力を示す反面、他の能力の発達と大きなギャップ・アンバランスが生じることもあり、理解と支援が必要です。
日本では、これまで傑出した才能を持つ児童・生徒に対する支援の枠組みが不十分でした。
そのため、文部科学省は有識者会議を設置して、支援の在り方について検討を開始。
この結果を受けて、政府は2023年度の予算案に8,000万円の予算を計上し、ギフテッド教育への本格的な支援を開始しています。
※参考|文部科学省|特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議|審議のまとめ
参考|文部科学省|令和6年度特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業採択団体一覧
「2E」という存在
ギフテッドの中には「2E(Twice Exceptional:2重に特別な)」というタイプもいます。
「発達障害➕ギフテッド」など、才能とともに学習面や行動面での困難を併せ持つ子どもたちです。
おもにADHDやASDなどの発達障害を持つことが多いですが、その他の疾病や特性をもつ子どもも同様です。
たとえば、数学には驚異的な才能を発揮する一方で、読み書きに困難があったり、注意が散漫だったりするケースなどさまざまなケースが考えられます。
2Eの子どもたちは、これまで才能に気づかれないまま「できない子」と誤解されることもあり、現在、支援の必要性がより高まりつつあるのが現状です。
もう一つのタイプとして「英才型」と呼ばれるギフテッドも定義されています。
これは学習面(知能面)だけでなく、芸術や運動、他者とのコミュニケーションなど、広い分野で優れた能力を発揮する子どものことです。
ギフテッドの特徴とは?
以上を踏まえて、ギフテッドの特徴をみてみましょう。
ギフテッドの子どもたちは、以下のような特徴を持っていることがあります。
- 圧倒的な記憶力や論理的思考力
- 抽象的な概念を早くから理解できる
- 感受性が非常に強く、倫理観や正義感が際立つ
- 周囲と話や関心が合わず孤立することも
- 大きく分けて「2E型」と「英才型」の2つのタイプがある
これまでの日本の教育現場においては、「手がかかる」「変わっている」と思われがちな面も、実は才能の裏返しであることが少なくないことが解明されつつあります。
同年齢の子どもと比べて、論理的思考力や抽象的概念の理解が高いと学校の授業がつまらなく感じたり、同世代の子どもと話が合わないことも多いようです。
周囲との違和感を強く感じることから、自分の能力を隠そうとする場合もあります。
ギフテッド教育とは?その内容と意義
出典:YouTube:文部科学省より
こうした現状を受け、近年、日本でも「ギフテッド教育」が着実に広まりつつあります。
「初めて知った」という方のために、以下ではギフテッド教育の目的や海外事情もあわせて見てみましょう。
ギフテッド教育の目的
ギフテッド教育は、子どもたちが自らの潜在能力を最大限に発揮できるよう支援することが目的です。
単に難しいことを学ばせるのではなく、「その子に合った学びの深さ・スピード」で教育を提供することが中心となります。
才能に合った環境が提供されないと、ギフテッドの子どもたちはフラストレーションを感じたり、不登校や無気力に陥ったりするリスクもあるため、個別対応が極めて重要です。
海外のギフテッド教育事情
アメリカでは州ごとに制度が異なるものの、多くの州でギフテッド教育プログラムが整備されています。
たとえば、才能を持つ子ども向けの専門学校や特別クラスの設置、またオンライン教材の活用によって、能力に応じた教育が進められているのが一例です。
National Association for Gifted Children(NAGC)などの団体が、政策提言や教育者の研修にも積極的に関与しています※。
こうした流れを受けて、日本においても徐々にギフテッド教育に対する政策が提言されつつあります。
※National Association for Gifted Children(英語)
日本の学校現場での試行錯誤
とはいえ、日本では、飛び級制度がほとんど導入されておらず、同年齢での一律教育が基本です。
そのため、ギフテッドの子どもたちにとっては物足りなさや息苦しさを感じる環境になってしまうことも多いようです。
一部の自治体や学校※では、探究型学習や発展教材、プロジェクト学習などで対応を試みていますが、制度化はまだ道半ばです。
これまでの取り組み
政府はこれまで、次世代人材育成事業の一環として、傑出した才能をもつ「ギフテッドの児童・生徒のみ」に、支援を行ってきました。
参考として、これまでの取り組み例を以下に紹介します(クリックでリンク先に飛びます)。
これに加え、今後は2Eを含めた「支援としてのギフテッド教育」の充実が拡充することが期待されます。
ギフテッド教育のメリット

ギフテッド教育のメリット1:個性を活かして成長できる
これにより、子どもは「自分らしくいていい」と主体的に感じることができます。
好きなことに没頭できる時間や環境が用意されることで、才能は自然に開花していきます。
ギフテッド教育のメリット2:社会的な活躍や貢献が期待できる
将来的には、科学者・芸術家・起業家など、多様な分野で早くから活躍する若者が増えることが期待されます。適切な支援があれば、社会にとって、これまで以上に貴重な人材となり得るでしょう。
これまでの教育支援では、周囲になじめずドロップアウトした子どもも、今後は能力に応じた(あるいはそれ以上の)教育支援を提供することで、本来の才能を存分に発揮できる環境が整うことが予想されます。
ギフテッド教育のメリット3:他者理解と教育多様性の推進
ギフテッド教育を通して、周囲も「子どもは一人ひとり違う」という視点を学ぶことができるでしょう。
これは、すべての子どもに優しい教育環境をつくるための第一歩につながることが期待できます。
ギフテッド教育のデメリット
ギフテッド教育のデメリット1:孤立感や周囲とのギャップ
同世代の子どもと価値観や興味が合わず、孤独を感じるギフテッドの子どもも多いようです。
その結果、学校生活になじめず不登校になるケースもあります。
ギフテッド教育のデメリット2:教育現場の対応が難しい
日本の教員研修ではギフテッド教育がほとんど取り上げられておらず、現場の教師がどう接すればよいのか分からないまま、支援が後手に回ることも多いのが実情です。
現場の教師でさえ、ギフテッドの子どもを理解できないことが少なくありません。
そのため、今後はさらに現場を含めた「ギフテッド教育」に対する理解が求められます。
ギフテッド教育のデメリット3:期待とプレッシャーのジレンマ
周囲の期待が大きくなりすぎると、本人が「失敗できない」と感じて苦しんでしまうことも。「才能があるから頑張れる」ではなく、「才能があっても心のケアが必要」です。
どんなに優れた能力があったとしても、完璧ではありません。周囲と違っていることを自覚しながら、悩みを抱える生徒もいることでしょう。生徒が抱える「期待とプレッシャーのジレンマ」を、いかにケアしていくのかが、大きな課題です
ギフテッド教育の日本における現状と課題
出典:YouTube:文部科学省より
文部科学省の方向性と課題認識
2022年、文部科学省は「特定分野に特異な才能を持つ児童生徒に関する有識者会議」を設置し、「審議のまとめ」を公表しました※。ギフテッド支援の必要性を明記し、学校現場への周知と教育の多様化に言及しています。
文部科学省では、令和の学校教育の柱の1つとして「個別最適な学び」をあげています。ギフテッドの子どもへの支援・指導も個別最適な学びの中で行っていくこととなります。
さらにこれに伴い、文部科学省は「特異な才能のある児童生徒への支援の推進」として事業採択団体をまとめ、ギフテッド事業への取り組みを開始しました。
現状は限られた地域のみの実施ですが、今後はいかに国民の認知を広げていくかが課題です。
※参考|文部科学省|令和6年度特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業採択団体一覧
制度設計と人材育成が今後の課題
今後求められるのは、教員研修の充実、専門機関との連携、そして全国一律での制度設計です。
特に地方では人材不足や理解不足も深刻で、自治体間での支援格差が大きくなっています。
支援の増加は、現場で働く教職員への負担像に直結します。現状でさえオーバーワークが懸念される中、専門職の確立や支援施設の設置など、新たな人材・設備投資が必要となることは間違いありません。
参照|みんなの教育技術|勤務校に「ギフテッド」が入学してくる! 教職員チームは、まず何をすべきか?
社会の理解と共感が重要に
ギフテッドは「特別な存在」として排除されがちですが、多様な才能を認める社会こそが真に成熟した社会です。保護者・学校・社会全体が連携して、「その子らしさ」を尊重する土壌づくりが求められています。
従来の価値観においては「変わった子」として扱われていた子どもが、現在的視点からすると「実はギフテッドだった」ということもあるでしょう。こうした誤解を防ぐためにも、社会的な理解や共感を得るための活動が求められます。
ギフテッド教育解説:まとめ
今回はギフテッド教育について解説しました。
ギフテッド教育は、ただの「特別扱い」ではなく、これまでの教育現場における「見直し」という部分が大きいのがお分かりいただけたと思います。
それは、その子どもの特性や可能性を正しく理解し、適切な環境で伸ばしていくためのアプローチですもあります。 日本でも少しずつ動き出してはいるものの、制度面や教育現場の理解・社会的な共感など、課題も山積みです。
ギフテッド教育について知っている人はもちろん、知らなかった方も、情報に触れ、日本社会全体のさらなる理解がますます必要となるでしょう。
最新記事一覧
- チャレンジスクールの志願申告書はどう書く?高校一覧や学費、倍率も徹底解説します!
- 少年鑑別所の入所数は増えている?少年院との違いや期間、相談窓口を簡単に解説!
- 要対協に守秘義務はある?メンバー構成や担当者の資格を解説!
- 認定こども園とは?わかりやすく解説!保育園との違いやデメリット、対象年齢は?
- 懲戒権の削除について簡単に解説!見直しの理由やしつけのあり方を考える
参考・参照資料URL一覧
・文部科学省|特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議 論点整理(案)〜令和3年〜
・日本ギフテッド協会
・日米ギフテッド協会(特性チェックあり)
・渋谷区ラーニング・リソースセンター
・2E教育フォーラム|文部科学省「特異な才能のある児童生徒の指導・支援」有識者会議
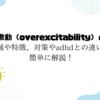



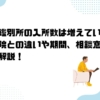


最近のコメント