就労継続支援とは?A型とB型の違いは?対象者や今後の展望は?障害福祉サービスも含めながらわかりやすく解説します!
この記事は就労継続支援について包括的にわかりやすく解説します。
就労継続支援は、大きく分けてA型とB型の2種類の支援があり、対象者や作業内容など、さまざまな面で違いがあることはご存じの方も多いことでしょう。
しかし、実際に支援をお考えの方や、あるいは周囲にの方の中には、よく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、障害福祉サービスを踏まえつつ、就労継続支援のポイントを紹介します。
また、国の施策に関するリンクも併せて紹介しますので、ご利用をお考えの方にとって、少しでもお役にたてれば幸いです。
就労継続支援とは?障がい者の働く権利を守る制度

就労継続支援は、2006年(平成18年)に施行された、障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスの一つです。
この制度は、一般企業での就労が困難な障がい者の方々に働く場を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行うことを目的としています。
就労継続支援の意義は、単に働く場を提供するだけではなく、この制度を通じて、障がいのある方々は以下のような機会を得ることができます。
- 社会参加の促進
- 経済的自立の支援
- 自己実現の機会
- 生活リズムの確立
- コミュニケーション能力の向上
こうした要素は、障がい者の方々の生活の質を向上させ、また、社会全体のインクルージョン※を促進する上で非常に重要です。
就労継続支援は、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの一つであり、就労移行支援、就労定着支援と並んで重要な位置を占めています。
特に、一般就労が困難な方々にとっては、自分のペースで働ける場所を提供する点に大きな意義があると言えるでしょう。
なお、就労継続支援を受ける際には、A型・B型に限らずアセスメント(評価)が行われます。
参考|厚生労働省|障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
※インクルージョン:お互いの個性を尊重しあいながら、社会に参画すること。
A型とB型:就労継続支援の2つの形態
就労継続支援には、A型とB型の2つのタイプがあります。
それぞれの特徴と違いを理解することで、利用者一人ひとりのニーズに合った支援を選択することができます。
就労継続支援A型:雇用契約に基づく就労支援
A型は「雇用型」とも呼ばれ、障がい者の方々を雇用契約に基づいて受け入れる形態です。
主な特徴は以下の通りです。
- 最低賃金が保証される
- 雇用保険や社会保険の加入対象となる
- 一般就労に近い形態で働ける
- 比較的障がいの程度が軽い方が対象
A型事業所では、製造業、清掃業、事務作業など、様々な職種が提供されています。
厚生労働省の2019年(令和4年)の調査※によると、全国で約4,500か所のA型事業所が運営されており、
約100,000人の方々が利用しています。
以下のいずれかに該当する方がA型の対象者です。
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業し、就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 就労経験のある方で、現に雇用関係の状態にない方
原則として18歳から65歳未満の方が対象ですが、65歳以上でも一定の条件を満たせば利用可能です。
※厚生労働省|令和4年社会福祉施設等調査の概況|施設の状況
参考|厚生労働省|障害者の就労支援対策の状況
就労継続支援B型:柔軟な働き方を可能にする非雇用型支援
B型は「非雇用型」と呼ばれ、雇用契約を結ばずに働く機会を提供する形態です。
主な特徴は以下の通りです。
- 雇用契約を結ばないため、最低賃金の保証はない
- 工賃(作業の対価)が支払われる
- 比較的障がいの程度が重い方も利用可能
- 作業能力や体調に応じて柔軟に働ける
B型事業所では、軽作業や手工芸品の製作、農作業など、多様な作業が用意されています。
しかしA型と比べると、より簡易的な作業内容が多い傾向にあります。
また、B型の対象者は以下のいずれかに該当する方です。
- 就労経験がある方で、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 50歳に達している方または障害者基礎年金1級受給者
- 上記に該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方
なお、B型は基本的に年齢制限がないため、幅広い年齢層の方が利用しています。
参考|厚生労働省|障害者の就労支援について
障害福祉サービスいろいろ
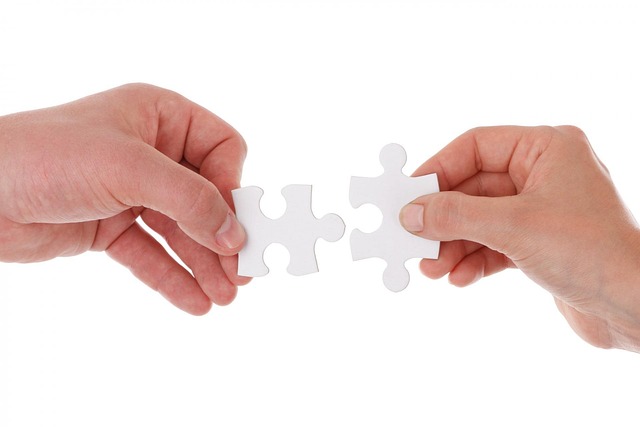
障害のある方々の生活を支援し、社会参加を促進するものとして「障害福祉サービス」があります。
本制度は、障害者総合支援法に基づいて提供される重要な支援システムで、個々のニーズに応じたきめ細やかなサービスを通じ、障害者の自立と尊厳ある生活を実現することを目指すものです。
サービスの種類と特徴
障害福祉サービスは大きく2つに分類されます。
一つは、個別の状況を考慮して支給決定が行われる「障害福祉サービス」。
もう一つは、各市町村が地域の実情に合わせて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」です。
さらに、障害福祉サービスは、
・介護給付費
・訓練等給付費
の2つに細分化されます。
介護給付費には、居宅介護(ホームヘルプサービス)や生活介護などが含まれ、日常生活の支援に重点を置いているのが特徴です。
一方、訓練等給付費は、就労移行支援や自立訓練など、社会参加と自立を促進するためのサービスをカバーしています。
利用者本位のサービス提供
障害福祉サービスの特筆すべき点は、利用者一人ひとりの状況に応じたサービス提供を行う点です。
例えば、生活介護サービスを利用する際には、障害支援区分の審査認定が必要となります。
これは、障害の特性や心身の状況を1〜6の段階で評価し※、適切なサービスを公平に利用できるようにする仕組みです。
また、2024年(令和6年)現在、この制度はさらに進化を遂げており、ICTの活用によるサービスの効率化※や、地域社会との連携強化など、新たな取り組みが始まっています。
※|障がい者(障害者)の求人転職情報・雇用支援サービス|障害支援区分って何?身体障害者が受けられる社会保障制度や医療制度について解説!
※厚生労働省|令和 4 年度障害者総合福祉推進事業|障害福祉サービス事業所等におけるICT
/ロボット等導入による生産性向上効果検証|株式会社インサイト(令和5年3月)
自立を目指す訓練と支援
訓練等給付費に含まれる就労継続支援B型や就労移行支援は、障害者の就労と自立を支援する重要なサービスです。
これは単に職業訓練を提供するだけでなく、社会適応能力の向上や就労後の定着支援まで幅広くカバーしています。近年では、テクノロジーの進歩に伴い、VR(仮想現実)を活用した職業訓練プログラムなど、革新的なアプローチも導入されつつあるようです※。
なお、次のものが訓練等給付費に該当します。
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助
※BRISE|職業トレーニング用VRソフトウェア「JobStudio(ジョブスタジオ)」
KSB瀬戸内海放送|VRやARなど活用し職業訓練 新しい技術で活躍を 香川
地域社会との共生を目指して
障害福祉サービスの究極の目標は、障害者が地域社会の中で自立した生活を送り、積極的に社会参加できる環境を整えることです。
そのため、共同生活援助(グループホーム)や自立生活援助などのサービスも提供されています。
就労継続支援の利用方法:一人ひとりに合わせた支援を受けるために

就労継続支援を利用するためには、一定の手続きが必要です。
以下に、利用までの一般的な流れと注意点を紹介します。
相談
まずは地域の相談支援事業所や市区町村の窓口に相談します。
ここで、自分の状況や希望を伝え、適切なサービスについてアドバイスを受けます。
障害支援区分の認定
B型を利用する場合、原則として障害支援区分の認定が必要です。
これは、障がいの程度や生活上の困難さを評価するものです。
サービス等利用計画の作成
相談支援専門員の協力のもと、具体的な支援内容や利用する事業所を決定し、サービス等利用計画を作成。
支給決定
市区町村に申請を行い、サービスの利用に関する支給決定を受けます。
事業所との契約
支給決定後、利用する事業所と利用契約を結びます。
サービスの利用開始
契約完了後、実際にサービスの利用を開始。
注意点
- 利用にあたっては、原則として利用者負担が発生します。ただし、所得に応じて負担上限額が設定されています。
- A型を利用する場合は、就労に関する能力や意欲の評価が行われることがあります。
- B型の利用には年齢制限(原則65歳未満)があります。ただし、65歳以上でも市区町村の判断で利用が認められる場合があります。
なお、不明な点があれば、遠慮なく相談支援専門員や市区町村の窓口に質問してみてください。
就労継続支援:今後の展望
ここまで、就労継続支援について紹介してきました。
最後に、今後の展望についていくつか見てみましょう。
さまざまな法整備が進み課題は解決しつつあるものの、今後もさらなる改善が進められる予定です。
工賃向上への取り組み強化
- 高付加価値商品の開発や販路拡大支援
- 企業とのコラボレーション促進
- ICTを活用した生産性向上
一般就労への移行支援の充実
- 段階的な就労移行プログラムの導入
- 企業との連携強化(実習機会の拡大など)
- ジョブコーチ制度の拡充
サービスの質の標準化
- 第三者評価制度の強化
- 好事例の共有と横展開
- スタッフの専門性向上のための研修制度の充実
多様な障がい特性に対応した支援の拡充
- 専門家との連携強化
- テクノロジーを活用した支援ツールの導入
- 個別支援計画の質の向上
社会的認知度の向上
- 啓発活動の強化(イベントやメディア露出の増加)
- 企業や教育機関との連携促進
- 障がい者アートや製品のブランディング強化
さらに、2024(令和6年)年4月から施行された、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」※は、障がい者の情報アクセスやコミュニケーション支援の強化を目指しています。
そのため、本法律の施行により、就労継続支援の現場でも、ICTを活用した新たな支援方法の導入や、コミュニケーション手段の多様化が進むことが期待できるでしょう。
※内閣府|障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進|障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
参考|厚生労働省|「障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性」(中間取りまとめ)概要①
参考|厚生労働省|障害者雇用対策の現状と今後の展望(令和2年12月)
就労継続支援まとめ
就労継続支援制度は、障がいのある方々の「働く」という基本的な権利を保障し、自己実現と社会参加を支援する重要な仕組みです。
この制度を通じて、多くの方々が自分らしい生活を送り、社会とつながる機会を得ています。
ご自身のライフスタイルや働き方への希望をじっくりと考えて、この記事でが豊かな社会生活を送るきっかけとなれば幸いです。






最近のコメント